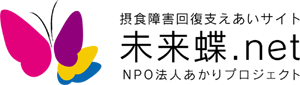HOME > わたしたちの声 > わたしたちのストーリー > Vol.10 紗江さん
私の半分~Ⅰ型糖尿病、そして摂食障害と向き合ったこれまでのこと
はじめに
私はⅠ型糖尿病患者だ。同時に、摂食障害者でもある。
糖尿病が発症して23年、摂食障害を発症して17年、今まで自分がかかえてきた苦しさや生きづらさ、そしてその基にあるものを、グループミーティングの場で言葉にしてきた。それができるようになったことが、何とか生きる力を後押ししてくれたと感じる。
そして今、心の底から湧き出てくるように、それらの言葉を紡ぎ合わせ、ここまでの自分の人生の物語をまとめなければならないとの、衝動に衝き動かされている。
私は、12歳の時にいじめに遭い、登校拒否になった。半年間におよぶいじめは、私に自己評価の低さと、人に対する恐怖感を、植え付けるには充分な経験だった。
中学には、ほとんど通わなかった。私は、人口2000人足らずの、過疎の村で育った。保育園から中学まで、クラスは一つだけ。よって、転校という選択肢は無かったのだ。Ⅰ型糖尿病を発症したのは、その頃のことである。
当然のことながら、学力が足りておらず、小6から4年間のブランクを埋める為に、今でいう、フリースクールの先駆けのような塾に通った。何故、そこを選んだのか? 他に選択肢が無かったからだ。そして私は、2年間そこに通い、とある高校に合格した。18歳で。
それは一種の成功譚のように聞こえるかもしれない。しかし、本当の苦しさはそこから始まったのだ。
Ⅰ型糖尿病と不登校
指先にぷつりと浮かんだ赤い雫を、機械に装着したチップに吸い込ませる。5秒後、チチッと小さな音がして、血糖値が画面に表示される。その値を見て、インスリン注射の単位数を決めるのだ。1日、5回。昨年までは、4回(超速効型を食事毎に3回、持続型を就寝前に1回)だったが、持続型を、日中の血糖値を安定させる為に、朝晩2回に分けて打つことになったのだ。
今から17年前、摂食障害にかかった当初、私の血糖測定器は、常にHiを表示していた。血糖値が650を越えると、Hiと表示される。つまり、18歳から数年間、私は、常時、血糖値が650以上あった、ということになる。
私は、12歳、中学1年生の時に、Ⅰ型糖尿病と診断された。始まりは風邪だった。37度台の熱が、ぐずぐずと2週間ほど続き、その内に異常な喉の乾きと、全身の気怠さが始まった。飲んでも飲んでも、乾きは癒えず、唾液で舌が口の中にはり付き、枕元に置いたペットボトルの水を飲みながら、夜中に何度もトイレに走った。そうこうしている間に、今度は体重が減り始めた。1日約1kg。1週間で5kg落ち、吐き気と頭痛で運び込まれた掛かり付けの医院で、私は糖尿病と診断された。
この医院は、糖尿病の専門医ではなく、過齢や肥満による、いわゆるⅡ型の糖尿病と、同じ治療法を指示された。食事と運動療法である。しかし、さらに体重が5kg落ち、血糖値が安定しなかったこともあって、別の病院を紹介された。二軒目の病院、そこで私は、初めてインスリンの注射を指示された。
その頃、私は、登校拒否の真最中だった。
糖尿病の発病は、私にとって、重荷であり、同時に救いでもあった。というのも、私が学校に行かなくなって以来、我が家は嵐の真只中にあったからである。
何とかして、学校に行かせようとする家族と、何としてでも、学校に引っ張り出そうとする学校側。担任の先生や友人たちが、度々家を訪れてくれたが、私は、時々保健室登校をする以外、登校することは出来なかった。
昨日まで笑顔でいたクラスメイトが、今日には背中を向けられる驚きと恐怖感。何よりも辛く、悲しかったのは、私の気持ちを受け止めてくれる、家族がいなかったことだった。
「その程度のこと、我慢出来ないでどうするの」「学校に行かないで、 将来どうするつもりなの」、果ては「学校に行かないなら、家から出て行け」「そんな子供に育てたつもりはない」「学校に行くことは義務なんだ。義務違反で警察に捕まったら、それはお前のせいだ」・・・。
今にして思えば、学校に行かせようとした家族の気持ちも理解出来る。20年近い時間が経って、母と当時のことを振り返った時、こう言われた。
家を居心地の悪い場所にして、何とか学校に向かわせようとしたのだ、と。
毎日毎日、怒り飛ばす父と、嘆き悲しんだ末に、家出までした祖母。学校と家との間に立たせられて、私を連れて自殺することすら考えたという母。ひたすら無関心を装う姉。
私は一人だった。家にも学校にも居場所を見付けられないまま、膝を抱えて、縮こまっているしか無かった。
当時の母の年齢を超え、母の立場を省みることが出来るようになった今なら、理解することが出来る。けれど、当時の家族に訴えかけたいことがある。自宅を居心地の悪い場所にする、その手法が通じるのは、家が安心出来る場所だと、体得出来ている人間だけなのだよ、と。
私にとって、病気が救いになったのは、家族にとっても学校側にとっても、理由が出来たからだった。「病気があるから」家にこもっていても、当然なのだ、と。
転院した病院先でも、血糖値が中々安定しなかった私に、親しく言葉を交わすようになった栄養師の女性が、転院することを提案してくれた。「ここの 病院はⅡ型の患者さんには対応出来るけど・・・」、Ⅰ型の患者は、私以外、診ていないというのだ。「日本国内でも有数の糖尿病の専門科がある病院があるから、行ってみたら」と。それが、現在の私が掛かり付けの病院である、K市のO総合病院である。
「入院しなきゃ駄目だね、これは」検査結果を見て、その先生は言った。彼は、驚きの余り口をきけずにいる私に、診察室のベッドに横になることを指示し、足の付け根の動脈に注射針を刺した。 「1日2回?駄目駄目、それじゃ。どうしても帰りたいって言うんなら、これを4回に分けて打ちなさい。でも、ベッドも空いているし、入院することを勧めるね。僕は」
私に選択肢は無かった。着のみ着のまま、入院病棟に放り込まれた私は、それまでとはまったく異なる治療法を指示された。1日4回の血糖測定(入院中には、10回採血、測定されたこともあった)と、インスリン注射。カロリー計算と運動療法。2週間の教育入院の間に、治療と講義を受けた私は、それらの方法を叩き込まれた。15歳の時だった。
Ⅰ型の糖尿病と、Ⅱ型の糖尿病の治療法は、基本的に同じである。だが、患者の絶対数が違っていた。入院した時、周囲は皆大人ばかりで、一人10 代半ばの私に、好奇心と奇異の目が集まった。それが何より辛かった。
実は、前の病院で、Ⅰ型糖尿病患者を対象にした、サマーキャンプの誘いがあった。けれど、私は、それを断っていた。同年代の子どもたちに対する、恐怖心が、拭い去れなかったのである。
塾、高校、そして過食の地獄へ
退院後、ときおり保健室登校をしていた私に、新たな出会いが訪れた。それが、最初に述べた塾の、N先生である。彼は、私のクラスメイトの家庭教師をしていた。その親御さんからの紹介だった。
両親は、勉強を教えてもらう以上に、病院に通院する以外は、部屋に引き込もっていた私の、話し相手としての役割を、彼に求めていた。彼は確かに、色々な話をしてくれた。高校進学の他に大検という道があること。彼は、情報薄弱な私たち家族の前に現れた、フランシスコ・ザビエルのような存在だっ た。けれど、私が、実際に彼に教えを請うのは、それから半年以上先、私が中学を卒業してからのことになる。
私が、N先生の塾に(その頃、彼は、家庭教師業を辞めて、塾を開校していた)通うことに決めたのは、進学の為の学力の向上の為だけでは無く、何よりも、逃げ場所を求めていたのだと思う。
その頃私は、祖母からのプレッシャーを、ひしひしと感じていた。糖尿病が発症して以来、祖母は度々「紗江は家にいて、体のことを一番に考えて、家のことを手伝ってくれればいいから」と、言っていた。それは私にとって、救いでもあったが、同時に、危機感を募らせることにもなった。(私、このままで大丈夫なの?)という思いである。
私の決断を、両親は喜び、祖母は顔を曇らせた。それは、祖父母に育てられ、家事手伝いをしていた私が、図らずも反旗を翻す結果となった。
塾には、月~金曜日の5日間、午後に通うことになった。午前中に、テキストの予習をし、午後に採点と次回に向けての補修を行う。週に5科目。学校に行かなくなってから、4年間分の勉強を、2年間で詰め込んだ。塾で過ごした2年間は、概ね楽しいものだった。
彼とは、色々なことを話した。金縛りのメカニズムから、宇宙への人類移住計画、「恋愛と結婚は違うのか?」なんていう私の質問に、彼が答えてくれたこともあった(答えは「違う」だった)。彼は理系の大学出身だったが、私は、文系の頭だったらしく、度々行われた模擬試験の結果は、社会が一番良かったりし た。その後、私は、当時県内唯一だった、単位制高校に合格した。
入学前の説明会の時点で、私は、不安に襲われていた。1クラス40名、1学年3クラス、120名。3学年合わせても100名に満たなかった、故郷の学校とは、大違いだった。
私は、ひどく緊張していた。3つ歳上という事実に引け目を感じ、今度は、失敗してはならない、と、自分に言い聞かせていた。また、同じことをくり返してはならない、と。結果的に、私のそんな思い込みが空回りして、自分で自分の首を締める結果になった。
高校入学と共に、私は家を出て、新生活を始めることになった。姉の勤め先と、高校の中間の町にアパートを借り、二人暮らし。分担して家事をやり、私は朝7時前に家を出て、片道1時間半の距離を通うことになった。
結果的に、私がせっかく合格した高校に通いきれなかったのは、人に対する恐怖感を、拭い去れなかったことにあるのだと思う。塾での2年間は、マンツーマンであり、同年代の人たちと、接する機会が無かった。加えて授業は、1日7時間あり、1日1科目を、集中して勉強していた私のやり方が、通用するはずも無かった。先生にもクラスメイトにも恵まれて、高校生活は概ね楽しかった。だが極度の緊張と完璧主義が、私を次第に摩耗させていった。体も、心も。
きっかけは、パンだった。その日、私は一人で部屋にいて、昼食用のパンを切っていた(炭水化物の計量は、糖尿病患者の基本だ)。
卵に野菜にトーストに・・・昼食を準備して、血糖値を測り、インスリンを打つ。いつも通りの食事を終え、後片付けをした後に、ふと、調理台の上のパンが目に入った。
気が付くと、袋を開け、パンを食べていた。手で裂き、指で引き千切って、貪り食っていた。我に返った私は、慌てててインスリンを追加し、運動に出掛けた。いつも行くスーパーへ、わざわざ遠回りをして。それでも、血糖値の上昇による、喉の乾きと頭痛は治まらなかった。
過食は加速度的に増えていった。暴走する食欲を、理性で止めることは出来なかった。パン、クッキー、チョコレート・・・それまで我慢していた炭水化物を、手当たり次第に詰め込んだ。近所にあるコンビニに1日3回通い、スーパーやパン屋さんを、何軒も梯子した。炊飯器で米が炊きあがるのを待ちながら、スパゲッティや乾麺をゆでた。単なるやけ喰いと違うのは、凄まじい自己嫌悪がセットになっていることだった。
食べたことによる満足感を、打消すように口に指を突っ込み、下剤を飲んだ。それに加えて、私の頭の中には、糖尿病を発病した当初の、1週間で5kg落ちた経験があった。折しも、巷では『低インスリンダイエット』なるものが流行っていた。インスリンは悪者とされ「インスリンは脂肪を貯め込 む」「高血糖は肥満のもと」などという情報が溢れかえった。
隠れて過食をしながら、その一方で、私は玄米食になった。勿論、そんなことで、血糖値の急上昇は止められなかったけど。上手く吐けなかった私は、インスリンの追加打ちを止めた。当然、血糖値は、うなぎ登り。常時、300、400は当たり前。ついには、一日中、血糖値がHiという有様になった。
当時の私は、命を危険にさらすことよりも、太ることが怖ろしかった。いや、血糖値が高くなることを、贖罪のように考えていた。皆の期待を裏切り、 また、同じことをくり返してしまったことに対する謝罪。それから目を背けるように、食異常を起こしてしまったことに対する贖罪。
自分を、死んでも当然だと思い込んでしまった為に、過食はますますひどくなった。食べ物のことが頭を支配し、片時も離れない。普通に食事を終えた後に、部屋に込もって過食した。 血糖値の急上昇による、喉の乾きと吐き気と目眩。たまりかねてインスリンを打ち、床に引っくり返る。緩慢な自殺行為を、日々繰り返していたようなものだった。
そんなことが度重なり、7号だった洋服のサイズが11号になった頃、家に戻ることになった。
糖尿病科の先生方には、当然、そんなことは理解されなかった。完治の無いこの病気では、合併症を防ぐことが、治療の目的である。
高血糖を抑える為に、インスリンの単位が増やされたが、打つのは自分である。一向に、症状が改善されない私は、心療内科の受診を勧められた。それで、行ったけれど、 処方された薬―食欲を抑制する薬、は全く効かず、先生との相性が合わなかったこともあって、数回で行かなくなってしまった。
その頃から、うつ状態や、家を飛び出すことが多くなった。
過食にお金がかかる上に、人に対する恐怖感が拭い去られていなかった私は、盛り場に行く訳ではなかった。(その頃は、常に母が同行していた)母と買い物、或いは病院に行く。商品を選んだり、会計を待っている時に、頭の中で、何者かがささやく。(ここは、お前のいる場所ではない)(これ以上、皆に迷惑をかけてはならない)と。私は、その声に突き動かされるまま、外に飛び出す。行き先など決め ていなかった。バスに乗り、電車に乗り、とにかく遠くへ。その衝動は、30を過ぎる頃まで続き、捕まったその足で、精神科病棟へ連行されたこともあった。
先生たちや仲間との出会い
精神科のU先生のもとへ通い始めて、今年で17年になる。「精神科」という響きに、躊躇する親を説得したのは、私だった。「心療内科」で お茶を濁している場合では無い、と感じたのだ。当時40代後半だったU先生は、何故か初めて会った時から、信頼出来た。そこから、摂食障害を克服する為の 長い長い物語が始まる。
(ここでちょっと一休み)
ここに、一冊の本がある。よしもとばななさん、三砂ちづるさんの共著である、「女子の遺伝子」だ。その中に、印象的な文章があるので、ご紹介したい。
まずは、ばななさんのお父さま、吉本隆明さんのお言葉、
「『親の育て方が悪い』というのは、子どもを厳しく叱りすぎたとか、逆に冷たく放っておいたとか、親のなんらかの言動が悪い、という意味ではありません。 そうではなく、子どもが育つ過程で、親との関係性によって傷つけられるのです。(中略)つまり、傷ついた親が子どもを育てるから、子どもの心も傷つく」
もう一つは、三砂ちづるさんのお言葉、
「若い女の人たちで、自分と母親との関係に問題があると言ってる人は山ほどいる。その問題があると言ってるのには二方向あって、一方向は親が非常に管理的な親。(中略)もう一つは、母らしい愛情を注いでもらえなかった、お母さんが勝手なことをやってて、自分のことをよくみてくれなかったというようなパターン。つまり世話をされない寂しさみたいなものです。管理することと足りないこと、それが愛情なのかどうかわかりませんけど、二つの方向があるなと思うんです」
(戻ります)
精神科のU先生の所に、通い始めて数回目のこと、私は、医大で開かれている摂食障害者の自助グループを紹介された。月に1回、第2土曜日に、本人と家族に別れて、ミーティングが行われる。初めて行った時のことは、忘れられない。講義室(註:正しくはゼミナール室)に、ぎっしりと妙齢の女性たちが集い、「言いっ放し聞きっ放し」のルールのもと、思いの丈をぶつけていく・・・。
皆の話を聞きながら、私は、涙が溢れて止まらなかった。同じ悩みを持つ仲間に、 出会えたという安堵感、過食および自傷行為という、自分の恥部をさらけ出しても、奇異の目で見られない。自分の番が来た時、私は震えと涙で上手く話せなかった。瞬く間に2時間が過ぎ、放心状態でいた私に、仲間の一人が駆け寄り、ハグしてくれた。その時に感じた驚きと、自分がここにいても良いのだ、という安心感と肯定感が、今も私を、その会に向かわせている。
精神科には、2週間に一度のペースで通っていた。投薬と現状報告。学校は休学して、家で治療に専念することになった。当初、すぐに解決するかと思われた「摂食障害」という病が、その後十数年に渡って、私に取り付こうとは、想像すらしていなかった。
祖母が亡くなったのは、成人式を終えて2ヶ月後、2月の末のことだった。晩年の祖母のことを思うと、今でも後悔で胸がきしむ。
私は、祖父母に育てられた。子供の頃の記憶は、母よりも、祖母と一緒にいた印象が強い。にもかかわらず、私は、摂食障害による、うつと高血糖で、部屋に閉じ込もっていた。晩年、病気がちになった祖母を、労ることも出来なかった。そして、そのまま、逝かせてしまった。
我が家の精神的支柱であり、 私の唯一の味方であった、祖母を失うと、私の症状はますます悪化した。リストカットや、溜めていた薬を、多量に飲むことも増えていった。自分の体を傷付けることで、精神的安定を得る、そんな不毛な日々が過ぎて行った。
当時、私は、糖尿病科の外来に通っていなかった。必要最低限のインスリンを、打っていただけ。受診して言われることは決まっている。母に頼んで、薬―インスリンや、注射針等をもらって来てもらったり、採血だけして診察は母任せ、自分は駐車場で待っていたりした。
そんなある日、1本の電話がかかってきた。当時、糖尿病科のセンター長をしておられた、A先生だった。私のカルテを不審に思ったA先生が、通常の診察の後の時間に、私を診てくれるという。指定された曜日に、おそるおそる私と母は出掛けて行った。 初めて入院した際に、遠目で見かけていたぐらいで、A先生に診察してもらうのは、初めての経験だった。糖尿病科は予約制であり、A先生の診察を受けているのは、中高年の経歴が長い患者さんばかり・・・要するに、とても敷居が高かったのである。
「やあ、お待たせしました」
約束の時間より、少し遅れてやってきた、A先生は、初老で大柄の、しかし少しも威張ったところの無い、気さくな先生だった。
緊張でがちがちになっていた私(たち)に、予想していたような、罵倒や非難の声は降って来なかった。カルテも見、私の話に耳を傾けながら、A先生は、落ち着いた様子で「あと3単位(インスリンを増やしても)体重は増えないと思うけどなぁ」と、おっしゃった。「カルテを見ていたら、何ヶ月も来ていないから、どうしたのかなぁ、と思っていたんですよ。でも、元気そうで良かった」とも。
こうして私は、A先生の、時間外診察を受けることになる。後になって私は、A先生が、ガンと糖尿病を患っていたことを知る。というのは、A先生が、それから2年足らずで、亡くなってしまったからだ。A先生の診察を受けつつも、過食が抑まらなかった私は、9ヶ月間、遠縁の親せきのもとに身を寄せることになる。その最中、一時帰宅した際に、診ていただいたのが最後になった。
A先生も、精神科のU先生も、私の過食という緩慢な自殺行為を、責めたり、止めようとしたりしなかった。ただ、淡々と耳を傾け、受け入れてくれただけだった。
過食をし、自責の念に駆られて自傷行為に走り、うつになる。その負のスパイラルから、抜け出せずにいた私にとって、お二人の存在は、何よりの救いだった。旅人のマントを脱がせた太陽のように、他人に対する恐怖心で、がちがちになっていた私の心を、温めてくれた。かつてA先生が、診察の最中に、私におっしゃってくれたことがある。
読書が趣味だという私に「紗江さんの経験を、書いてみてくれないかな。すごく興味があるし、僕は読むよ」と。その言葉が、私にこの話を書かせる、一つのきっかけになった。
A先生は、こんなこともおっしゃっていた。糖尿病の治療には、医者と栄養士と精神科医(または心理療法士)、三位一体で治療に当たるのが理想だと。残念ながら、糖尿病の患者数が爆発的に増えてしまった昨今、中々理想通りには行かないのだけれど。
U先生の診察を受けながら、自助グループにも通っていた。だが、私は次第に、疎外感を感じるようになっていた。原因は、私が「吐けない」こと、 そして、糖尿病があることだった。さまざまな本を読み、また、先を行く先輩方の経験談から、導き出された、摂食障害者にとっての回復とは「摂食障害も自分の個性と認めて、共に生きていくこと」だった。しかし、私が過食をすることは、死に直結することだった。その矛盾。
ようやく見付けた居場所から遠去かっていくのに比例して、過食の量は増えていった。本当は(私の)摂食障害の根底にあるものは、もっと根深いものだったと、気付かされるのは、もっと先のことになる。
恐怖の眼科治療と新たな出会い
「ピンチはチャンス」だという人がいる。チャンスとまでは行かないけれど、私が、過食をセーブするきっかけになったことはある。合併症の発症である。
それは、突然起こった。目の表面の、そして奥の、あまりの痛みに、目を開けていることすら出来ない。頭痛と吐き気が一晩中続き、脂汗を流す私は、 母に連れられて、通っている総合病院の眼科を受診した。診断は「ぶどう膜炎」。眼球へ3回注射し、6種類の眼薬を毎日4回点眼した。2週間に一度通院し て、視力検査と眼底検査を行った。
そうこうしている間に、糖尿病の三大合併症の一つである網膜症が発症した。
網膜症の治療は、レーザー治療だった。出血した眼底に、レーザーを照射された。痛みはぶどう膜炎に比べれば、少なかったが、突き刺さるような痛みがあり、また、毎週末、週に2回通わなければならなかったのが辛かった。(仕事を犠牲にして私の通院、入院、暴走に付き合ってくれた、母には改めて御礼を言いたい。どうもありがとうございました)その上、今度は、白内障が発症した。
「このままでは、これ以上レーザーが打てません。(白内障の)手術をしましょう」
主治医のS先生は言った。美人でたおやかな雰囲気を、良い意味で裏切る、肝の座った凄腕の先生だった。白内障は、目の中の水晶体が濁る病気である。その表面の濁りが邪魔をして、出血している場所が特定出来ない、だからレーザーが打てない、ということだった。
発症してから入院までの、2ヶ月ほどの間は、恐怖の連続だった。大好きだった本が読めない、テレビが見られない。料理をするにも手もとが見えない。買い物に行っても、財布の中身が判らない。中でも大変だったのは、インスリンの注射と、犬の散歩だった。単位の数値が判らないので、カチ、カチ、カチッという、小さな音に耳を澄ませて単位を合わせた。
我が家には現在13歳のE・コッカーがいる。彼を選んだのは私なのだが、その時ほど、彼の真黒な毛並みに、感謝したことはなかった。道路の白線が、見えないのだ。グレーや白色は道路と同化してしまう。それらの色のハイブリッドカーの接近に気付かずに、道路を渡ろうとして、クラクションを鳴らされたことも、度々あった。
2006年の1月末に、私は眼科病棟に入院した。6人部屋。不安と緊張と「ベッドが空いたので1日早く来て下さい。午前中に」と言われたのにもかかわらず、午後まで入院がずれ込んで、待ちくたびれていた私は、不機嫌そのものの顔で、部屋に入った。そこに彼女がいた。Iさんとの、出会いだった。
彼女は、中々の強者だった。何と、部屋にゲーム機を持ち込み、備え付けの小さなテレビでドラクエをやっていたのである。好奇心を抑えきれずに、 彼女のベッドに近付き「イオナズン(ドラクエの呪文)って出来る?」と、聞いたのが、話すきっかけだった。1つ歳上。糖尿病有り。同年代の糖尿病患者に出会ったのは、私も、彼女も初めてだった。
明るく姉御肌の彼女は、病室内の、ムードメーカーだった。後にも先にも、あれほど笑い声が響いていた病室を、私は、知らない。連絡先を交換しあい、一足先に、Iさんは退院して行った。
手術は週に一度ずつ、両目行われた。文明の進化とは怖しい。切れ目を入れた水晶体から、濁ったそれを吸い取り、折り畳んだ眼内レンズ を入れる・・・説明を受けた時には、気が遠のきかけたが、S先生は、それを30分もかからずにやり終えた。翌日、ガーゼを取った時の感動は、忘れられない。霞がかかっていた眼の前が、一挙にクリアーになった。その後もレーザー治療は続き、右目にはときおり痛みが走るが、7年経った今、私の視力は、日常生活に差し障りが無いほどに回復している。
2006年には、もう一つの出会いがあった。
手術を終えて退院したものの、外出出来ず(手術を終えた私の両目は、光に極端に弱くなっていた。雪の照り返しが特に駄目で、蛍光灯が爛々と光る夜のコンビニや、大型家電ショップも然り、である)家に閉じ込もっていた私に、一つの吉報が届いた。
トリノオリンピック。荒川静香さんの金メダル獲得。
衝撃的だった。この世の中に、これほど美しいものがあるのか、と思った。それは食べ物のことから頭が離れた初めての経験だった。私は、一日も飽きずに荒川さんの演技をくり返し見つめ、来たるべきフィギュアスケートのシーズンの幕明けを待った。そして、浅田真央さんの演技と出会った。浅田真央さんの、衝撃的なデビューを私は知らない。白内障が進んでいて、テレビとは没交渉だったからだ。だから、私が知る浅田真央さんは、笑顔よりも、悲しい顔の方が多かった。
明けた2006シーズン、私は、安藤美姫さんの快進撃に目を見張った。オリンピックの時とは別人のように、引き締まった表情、体付き。次々と高難度のジャンプを決め、情感溢れる演技で、ついには世界女王の座を射留めた。その陰で、銀メダルを得たものの、浅田真央さんは、懸命にもがいているように見えた。私が浅田真央さんのファンになったのは、2007シーズンだったと思う。その時、彼女はジャンプのミスがあったものの、ショートで首位に立った。しかし、同じジャンプのミスをくり返してしまったという後悔から、彼女は涙を流した。単純に順位を喜ぶのではなく、自分の納得のいく演技を追求して行く、その真摯な姿は、7年経った今でも、決して損われていない。さまざまな困難を経て来た彼女たちが、ソチで集大成の演技を見せてくれることを、私は切に願っている。
Iさんとの交流は、退院後にも続いていた。
同じような経歴をたどって来たのにもかかわらず、Iさんはポジティブだった。病気に正面から取り組み、且つ人生も楽しんでいる。過疎の小さな村に住んでいた私にとって(また、対人恐怖症がある身にとって)電車で彼女の住むK市内に行くのは、ちょっとした小旅行だった。彼女の家に泊まりに行ったり、 食事をしたり、映画を(『武士の一分』だった。手術後の私たちにとって、徐々に視力を失って行く主人公の姿は、臨場感がありすぎた)見に行ったり、泊まりがけで他所の県に行き、私が好きなアーティストのライブに、出かけたりした。(私が一人で新幹線に乗れるようになったのも、彼女のお陰だ)
電話は毎日。内容は、彼女が貸してくれたゲームのことや、他愛のない世間話。30になって、私はようやく、世間並みの楽しみを享受することになる。今までは、 滅多に起きなかった『低血糖』という症状が起きるようになった。(インスリンが効き過ぎて、血糖値が80以下になり、ひどい場合は昏睡を引き起こすこともある)それも、ほぼ毎日。インスリンの単位も減り、全てが上向きになるかと思われた。
しかし、原因不明の吐き気に、襲われるようになったのは、この頃からだった。吐く。とにかく、吐く。固形物を全て吐き出し、唾液が胃に溜まると吐き、終いには、度重なる胃酸の逆流で、食道がただれ、茶色い血を吐いた。
診断は、糖尿病の合併症の一つである神経障害。絶食と点滴と投薬治療で、1週間ほどで退院出来るのだが、いつ症状が現れるか判らない。(昨年は、5回入院した)結果、今の私は、6種類の精神科の薬の他に、3種類の糖尿病科系の薬を、 飲むことになった。
Iさんが言った言葉で、印象的なものがある。それは「諦める」という言葉だった。初めて聞いた時には、意味がよく判らなかった。
私にとっては、マイナスなイメージしか無く、むきになって食ってかかったような気がする。けれど、精神科のU先生に「あなたは病気(糖尿病)を受け入れていない」と言われ続けて、その言葉が「受け入れる」と同意語であったことに気付いた。
「無理なことは無理だって諦めて、先に進むしか無いんだよ」様々な経験をくぐり抜けて来た、彼女だからこその言葉だった。今は、疎遠になってしまったけれど、Iさん、あなたの生き方は、今も私の目標です。
疎遠になっていた自助グループに、再び行くことになったのは、震災がきっかけだった。震災後、避難を余儀なくさせられた我が家だったが、それは逆に、自助グループの会場に近付くことになった。
発症当時の凄じい食欲は抑えられていたが、うつの波と自傷行為は消えずに残っていて、それを解決させたかった、同じ悩みを持つ仲間の言葉に、耳を傾けてみたくなったのである。
久々に行ったそこは様替わりしていた。会を訪れる人々―かつては、本人と家族のミーティングは別れていた―の減少によって、会が一つに統合されていたのだ。そこでは、参加者の発言に対して、スタッフの方々がアドバイスをして下さる。
摂食障害を発症した、お子さんの悩みを、涙ながらに語る親御さんと、真摯に受け止める先生方の話、並びに母の発言を聞いている間に、私の内で何かが変わり始めた。伝えたい、訴えかけたいという気持ち―それは、他ならぬ、母に対する想いだった。私は数年前から、精神科に通う傍らカウンセリングを受けている。その時の経験が、一つに重なり合う感じがした。
おわりに、もう一度家族を
いつからなのか判らない。私は、私と両親、私と姉の間に、深い溝を感じていた。底がどこまであるのか判らない、深くて暗い溝の存在を。
両親と姉は言う。「家族なんだから、迷惑をかけてもいいんだよ。気を遣わないで、思ったことを言っていいんだよ。家族なんだから」
でも、と私は思う。「家族とはいえ、守るべき最低限のルールがあるんじゃないの? 家族とはいえ、遠慮が必要でしょう。時には」
私は祖母に育てられた。十代で結婚した母は、翌年姉を、21歳の時に私を出産した。母は、姉と、生まれて間もない私を祖母に託し、お勤めに出た。とり立てて珍しくもな い、ありふれた話だと思う。
けれど、私は、3歳の時まで、自分を男だと思って育った。青色や緑色の服を着て、自分のことを「ボク、ボク」と言っていた。髪を短く切り、紺色の長袖長ズボンで走り回っている、当時の写真が残っている。逆に姉は、赤色の服を着せられていた。保育園に入り、否応無しに「女の子の」 赤色の帽子を被せられた私は、強烈な違和感を感じて困惑した。毎日のように保育園でおもらしをし、毎日のように「行きたくない」と泣き喚いた。大げさかもしれないが、それは、生きて行く上での根幹にかかわる闘いだった。それまで信じてきたことを、180°転換させなければならなかったのだから。
兄弟がいる人は、誰もがそうなのかもしれないが、私は、姉に対抗意識を燃やし、姉より秀でた人間になろうとしていた。読書、お絵描き、お習字・・・4つ歳上の姉には、勉強で勝てるはずもなく、私は、それらに力を入れた。そのくせびびりだった私は、いつも姉の後ろをくっ付いて回り、うるさがられていたのだけれど。
小学校に上がり、初めて返って来た算数のテストは、100点満点中80点だった。それを見せた時の、祖母の言葉は忘れられない。
「あと2点だったな」と言われた。母の反応がどういうものであったのか、それは忘れてしまったのだけれど。当時の私の生殺与奪権を握っていたのは、母ではなく祖母だった。
とはいえ、暴力を振るわれた記憶は皆無である。祖母は愛情に溢れた人だった。学校から帰ってきた私に、かぼちゃを煮たり、 おむすびを握ってくれた。じっとしていることが嫌いで、いつも何か仕事を見付けては、動き回っていた。花と畑仕事を何よりも好み、一年中、日焼けしていた。ただ、女の子を育てた経験が無く、他人との比較対照でしか、幸せを確認することが出来なかった、というだけだ。
祖母を喜ばせることが、母を喜ばせることにもなると、信じて疑わなかった。それが私の思い込みだったと発覚したのは、最近のことである。テストで 良い点数を取ったり、絵画や習字で賞状をもらって来ても、母は大して喜ばなかった。「あ・・・そう」そんな感じだった。後になって理由を問うと、「おじいちゃんやおばあちゃんが、充分誉めていたから、私まで誉めなくてもいいと思って」というものだった。
でもお母さん、私は、いつもいつも、ただあなたが喜ぶ顔が見たくて、頑張っていたんだよ。
学齢に達した私に、祖母は、事ある毎に「男に負けないように」と吹き込んだ。「男に負けないように勉強を頑張れ。男に負けるな」と。ちなみに、祖母から私への遺言は「結婚なんかするな」というものだった。
小6の時に私が受けた、いじめの原因は、知らず知らずの間に、小学生とはいえ、「男の領域」に踏み込もうとした、私に対する反発だったのかもしれない、と今になって思う。けれど祖母は、私が生まれた時、後継ぎを欲しがっていた。二人育てた経験がある、男の子の。
摂食障害になり、カウンセリングを受けて、自分の過去を振り返って行くに当たって、導き出された(私なりの)答えがある。
一つは、摂食障害を通して、愛情を確認していたということ。こんなにも、みじめな、無様な、最低な自分をさらけ出しても、大丈夫?見捨てない?私のこと、嫌いになったりしない?と、訴えかけていた。怒られるのが判っていながら、同じイタズラを繰り返す子供のように。
父に言われて、一つ、悲しかったことがある。とある年の、大晦日のことだった。家族が、こたつで紅白を見ている最中に、私は裸足で家を飛び出した。不思議と、寒さも冷たさも感じない。雪がうっすらと降り積もった大地を、私は、川に向かって歩いて行った。「何やってるんだ!!」追いかけてきた父に、引き留められた。「お前は、親を困 らせて喜んでいるんだろう!!」そうではない。当時の私は、本気で、自分がいなくなってしまうことが、家族の為だと、信じて疑わなかったんだよ。
支配する母と放任主義の母、私には、二人の母がいた。勿論、祖母と母のことである。
祖母は強い人だった。病弱だった祖父に代わって世間を渡り歩き、二人の息子たちを育ててきたノウハウを、私たち姉妹に、母に、伝授しようとした。自分が歩んできた道に、自信と誇りを持っていた。そんな祖父母の監視下で、十代で結婚した母は、大変きゅうくつな想いを味わっていたという。
放任主義とは言っても、過疎の村に娯楽がある訳ではない。ママさんバレーや、PTAの会合といったものだった。私が幼い頃の記憶の中の母は、いつもぴりぴりして いて、話しかけるのも怖い雰囲気だった。だから、私は、祖母になついた。
「私が、おばあちゃんにべったりで、嫌じゃなかった?」という質問に、母は、「うとましく思っていた時期もあった」と言った。その瞬間、目の前が真暗になった。でもね、お母さん、そんな状況をつくり出していたのは、あなただったんだよ。
私が、幼い頃から抱えて来た、生きづらさの原因が、女性としての生き方を封じ込めて来た、祖母の教育方針にあるのではないか、と気付いたのは、今年に入ってからのことだ。
祖母は「こんなはずじゃない」と思って、生きてきた人だった。目指していた看護師という夢を、戦争で諦めざるを得なかった。結婚はしてみたものの、過疎の村に引っ越しを命じられ、頼りにしていた夫は病弱、女手一つで息子たちを育て、世間の矢面に立たざるを得なかった。その経験にプライドを持って生きてきた祖母に育てられた為に、私は、女性という自分のジェンダーを、受け入れられずに育っていた。摂食障害の治療の基本である、「ありのままの自分」を受け入れることが出来ずに。
しかし、である。女性として擁護されるのではなく、男の仮面を被って生きざるを得なかった、祖母の悲哀に思い至った時、私の内で何かが変わった。
「傷付いた親が子供を育てるから、子どもも傷付く」
私は、愛されていなかった訳ではない。
ただ、皆、必死だったのだ。
それが、17年間におよぶ摂食障害の末に、私がたどり着いた答えだった。
(2013/12/10 文 紗江さん)