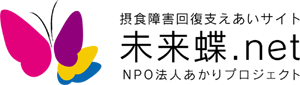HOME > いろんな人の声 > いろんな人に聞いてみよう! > vol.2 文化人類学者 磯野真穂さん
いろんな人に聞いてみよう!
第2回は『なぜふつうに食べられないのか』著者の磯野真穂さんにお話をうかがいました。
世間一般に「摂食障害」と呼ばれる人たちを「ふつうに食べられない人たち」と捉え、文化人類学的な切り口から、主に「食」や「生きること」の本質と照らし合わせながらこの現象を紐解いていらっしゃいます。
インタビューではご著書の内容について事前にお送りした質問にお答えいただいたり、ご研究の背景にある磯野さんご自身の生き方考え方にも迫りました。
(インタビュー リカバリーフレンド いづ 2015/11/21 記事アップ 2016/1/4)
★『なぜ、ふつうに食べられないのか』で語られているポイント★
●「ふつうに食べられない」状態とは、他者ともっと豊かに繋がりたいと願った人たちが結果的に食のハビトゥス(※1)を流出し、すなわち他者との紐帯を豊かにしていく術を失い、願いとは逆の方向に陥っている状態である
●「個」を「治療」しようとする医療は自然科学的な時空間、専門的言説の時空間にあり、食の準拠点(※2)がローカルな時空間から消えていることに注目していない。そのアプローチはともすると本人が陥っている苦しみに拍車をかける可能性もあり得る
●社会文化的なマントをはぎとったところにある「個」の問題としてこの現象を位置付けようとする視点ではなく、現在の社会がどのように個々人の食に影響を与えるのかを深く見ていく必要性がある
※1「食のハビトゥス」(身体知)
ハビトゥスとは、ありふれた行動が、当たり前にできるために必要となる様々な知識が身体化された状態(身体知)のこと。たとえば食に関して言えば― ・イスとテーブルがあるレストランでは床には座らずにイスに座って食事をとる
このように何をどうやって食べるかは、実は場面場面に応じて細かく決められている。しかし私たちは、その場その場に応じて、どのような食べ方が適切かを瞬間的に判断することができる。これを可能にしているのが食のハビトゥスであり、それがあるからこそ、他者とともに食べ、その他者と社会的な関係を作り上げ ていくことが可能になっている。
錨を下すことで、船が海の中でもある程度安定するように、食もある場所に錨が下されていることである程度の安定を保つ。これが本著でいう「食の準拠点」のこと。拙著では「食のハビトゥスに準じて食べること」イコール「日常生活の中に食の準拠点を置いて食べること」としており、ふつうに食べられない人たちは 日常生活というローカルな場ではなく、体重やカロリーといった自然科学の時空間や、原因は母親のせいというような専門的言説に食の準拠点が移動している、 と捉えている。
Q1.一当事者の経験から「ふつうに食べられない状態」から楽になるために、
・社会・文化とは絶対的なものではなく、自分のものさしで感じ取り選んでいい(現在の医療を疑うことも含め)と本人が腑に落ちるためのアプローチ
・そのために「自分の感覚」を受け入れたり誇りを取り戻すためのアプローチ
のように「個人」に目を向けるアプローチで有効なものもあると感じます。たとえば身体の感じを注意深く探って言葉を見出す「フォーカシング」、認知をより楽なものにしていこうとする「認知行動療法」、人間関係に目を向ける「人間関係療法」、自分の気持ちを表現する「自助グループ」などについてどのようにお考えでしょうか。
ふつうに食べられない人たちの食に、できる限り近づいてみたいと思った
-事前にお渡しした質問の中で、今日一番お聞きしたいことはQ3です。磯野さんの人となりって言うか、どんな背景があって摂食障害のご研究をなさったり、文化人類学の世界に身を置いていらっしゃるのかを垣間見ることができればうれしく思います。よろしくお願いします。ではまずQ1、Q2あたりから…
摂食障害の調査って星の数ほどあるんですけど、当事者の人から見た食べ物とか、当事者の人が食べている渦中でどういう経験をしているかっていう調査はほとんどないんです。そこに着目したのがこの本です。
-そこに着目しようと思ったのはなぜですか?
そういう研究がされていないからっていうのが一つと、あとはものすごいたくさん治し方に関する研究や本が出ているのに、根本的な解決に何も結びついていないように見えたから。
-まだ掘り下げられていないところにメスを入れてみたいっていう?
摂食障害の研究っていうのは治療ありきの研究になっていて、「これは治療すべきものである」という前提があるから、「じゃあその問題行動を起こしている原因は何なのか?」っていうところで、生物学的、心理学的、社会学的な原因論の追究がずっと行われてきたんです。
でも、そもそもわたしは過食・拒食っていう状態を病気って捉えるよりはある種の技(わざ)として捉えているところがあって、いったいその技を駆使するときに本人はどう思って、どう感じているんだろう、というところがすごい抜けてると感じた。治療にとどまらない視点を提示したくてこの本を書きました。
-治すべきものという前提で原因論が研究されてるっておっしゃったけど、すべての病気と言われるものはだいたいそうなのかなっていう気がするんですけど
うん、やっぱり自然科学的な思考っていうのはそうでしょうね。人文社会学的な思考っていうのは、原因論よりも当事者にとってどう見えているのかに着目する。文化人類学のスタンスをとっている研究っていうのはそういうアプローチをとっています。
たとえば慢性の病気を持っている人なら、原因論追究っていうよりはその人は病のことをどう見ているのかっていう研究がなされている。
-慢性の病気は原因追究じゃないアプローチがすでにされているけれど、摂食障害はそうじゃなかった、という理解でいいですか?
摂食障害のライフストーリーみたいなものはあるんですよ。でもやっぱり家族歴みたいな本人の背景に着目していて、「食べる」ことには注目していな い。
つまり、拒食や過食は「食べる」っていうことの乱れであるにもかかわらず、そこがほとんど注目されていないという変な逆転現象が起こっていたのをおかしく感じていました。
従来のアプローチだとどうしても、個人を分割して、「異常」な要因を探していくんですよね。でも個人を分割してしまうと、個人のまるごとの体験からはどんどん遠ざかってしまう。だから、分割しないでまずはこの本人が何を体験しているのかを本人に直接聞いてみようと。
-それって文化人類学独特の?
それ以外の学問でもやっているけれど、文化人類学がそこを徹底しているのは間違いない。正常・異常とかそういうことの前にとどまって、本人に見える世界を見て行こうという。それをわたしは摂食障害にあてはめてみたんです。
-それをすることで、例えば原因追究のアプローチだったら、より良い治療法に結び付けようとすると思うんですけど、文化人類学のアプローチだとどこに行き着こうとしているんでしょうか。
それは良く問われるんです。でも逆に質問してみたいです。なんでそんなに原因を探したり治療法を探したりしなくちゃいけないんですか? 人を見たり人を理解することって、別に原因を探すことでも治療法を探すことでもないとわたしは思うんですけど。
治療していくってアプローチは、「ふつうに食べられない人たちはそもそも楽になりたくて治療法を探してる」って前提に自動的に立つことになってしまう。
-つまり楽になるとかより良い治療に結びつけるというよりはとにかく理解したい…
理解したいっていう言葉自体かなりおこがましい感じがする。、むしろ何が起こっているのかを明らかにする、できる限り近づいてみたい…-うんうん、それはなんだかとっても本能的というか、人間の根本的な欲求のように思いますね。目の前のこの人のことをもっと知ってみたい、近づいてみたい…
楽になる方法をあえて考えるなら、自分の身体と共にいることを提示したい
「摂食障害」は現象としては似ていても、それに到達するプロセスって10人いたら10人違うと思う。
それを現象が同じという理由でひとまとめにし て「摂食障害」と名付け、それに対応する治療法がありますっていうこと自体わたしはなんかヘンだと思う。だからわたしはあんまりこうやったら治るとか、こうしたらいいですよっていうのは言いたくない。それは現実を捉え損ねていると思う。
-うんうん、磯野さんがこの本で伝えたかったことはこうしたらいいとかそういうところではなくて、一つの視点みたいなものを提示してくださってるんやなって思って読んだからここ(Q1とQ2のこと)はすごい欲張りな質問やなという自覚はあるんです。
でも一当事者として、こういう視点をお持ちの磯野さんやったら例えばどんなふうにイメージなさるのかなというちょっと純粋な興味からです。
まあ、でも考えてきました(笑)。
-わあ!やったあ(笑)。たぶん本を読んだ楽になりたいって思ってる人はたぶん「じゃあ磯野さん、わたしどうしたらいいんやろう」って思うと思う。
解決法は提示できないので、本人がいいとこ取りをして応用して、自分なりの解釈をしてくれるのがわたしはベストだと思う。
いわゆる体重に捉われていたり、過食の人たちって体重に救いを求めてみたり食べ物に求めてみたり、救いをアウトソーシングしてしまってるじゃないですか。助けを外に求めてしまう。家族モデルにはまってみたりとか。そういう風にすること自体がちょっと問題だと思う。自分である程度見つけていくのがわたしは究極だと思う。
-ちまたにそれこそいっぱいある治療法の本とか情報とか、これのいいところ、この自分に合いそうところっていうふうに貪欲に組み合わせていく…
というか、むしろバカにするぐらいがちょうどいいんじゃないですか?
-バカにできたらもうそれは楽になってるってことだと思う(笑)。
なるほど(笑)。そういう前提の上であえて言うならですけど、「自分の身体と共にいることの重要性」は提示したいと思います。
-それは具体的には?
本に書いたこととも関わるけれど、自分の身体を外の視点から捉えるのではなくて、自分のものとして捉える考え方が大事だと思う。
たとえばカロリーとか体重とかで自分を見てみるのもいいんだけれども、カロリーで食べ物をとらえないときの自分はどうやって食べていて、そのとき自分はどういう感じがするのか。体重のことを考えない時、自分はどういう感じがするのか。言い方を変えると、自分の身体を他の指標に預けない。
「食のハビトゥス」っ ていうのは、言ってみれば環境と共に食べながら生きていくための身体知なんですよ。ちっちゃいときから食べ方について繰り返し学び、知らないうちに自分の社会環境と共に食べ、自分を生かすっていう方法をわたしたちは身体の中に溶け込ませているんだけど、摂食障害に陥った人は、それを簡単に手放してしまっている。
それは自分の身体と共にいないってことだと思うんですよ。自分の身体を外から見続ける。それをやっているとすごく辛いと思う。
-自分の身体と共にいるっていうのはすなわち「食のハビトゥス」を流出させていないということとイコールですか?
厳密にいうと違いますが、大枠としてはそんな感じでいいと思います。
-「食のハビトゥス」が流れ出た状態っていうのがすごい辛いと思うとおっしゃったのはどうしてそう思いますか?そういう経験がありますか?想像ですか?
ダイエットとかしてたときはそういう感じだったと思う。常にこれは何カロリーだろうとか、これを食べたらどのくらい太るとか、そういう思考でいるから、ある種自分の心が未来にいっちゃっている。
だから自分の今ここと一緒にいられない。常に自分は未来にいて警告を発するみたいな状況になって、今ここの自分の感じ方を封印しちゃうから、そういう状態に陥らないことはすごく重要だと思う。
だからわたしはあまり体重を計らない。カロリーとかも見ない(笑)。
-あはは(笑)
たまにはいいけど、そういうことばかりをやって生きてどうするの?って思う。
そういうことを気にすることで自分の身体を常に監視するような状態で生きていてもわたしは全然楽しくない。それよりもむしろ、自分は今ここで何を思っているのかを大切にしたいから。
-それが磯野さんがおっしゃる自分の身体とともに生きるということなんですね。
ちまたに出ている情報は小馬鹿にしていい
具体的な方法を一つ提示するとすれば、ちまたに出てる情報を小ばかにしてみるっていう。
-ああいいですねえ。
たとえば、こういうの食べると健康になりますよとか、こういうエクササイズをしたらこうなりますよ、あなたも幸せになれますみたいな情報って社会にあふれかえっているわけなんです。ですけどこれは資本主義的なシステムにうまく乗ってるマーケティングなので、ちょっとここを疑う。
たとえば科学的うんぬんって言っても、科学的な現実なんて10年も経てば変わっちゃったりすることもあるわけで、そういうものにいちいち心を左右されない、「ふーん」みたいな感じで小ばかにする抵抗力が重要だと思うんですよ。
-なるほどね…。それはわかりやすい。
たとえば拒食や過食で困っている方って、かなり食べ物についての情報を気にしますよね。
抗生物質を使った肉は一切食べてはならないとか、マーガリンを食べるなんてもってのほかとか、有機農法の野菜じゃないといけないとか、もう挙げだしたら際限がないくらい。でもちまたにあふ ているそういう情報をうのみにしたら何も食べられなくなっちゃう。
そうじゃなくて、そういうものっていうのは一体どういう意図で発せられているんだろうなっていう形で、外から入ってくる情報に対して自分でバリアを張ってしまうみたいな、そういう抵抗力っていうのはわたしはすごく役に立つと思う。
-それは具体的にどうしてなんでしょう。
たとえばマーガリンをたくさん食べると、○○という病気になりやすいというデータがあるとする。でもそれはあくまでもそういう傾向がある、ということであって、マーガリンを食べたあなたに当てはまるかはまったくわからない。
統計と言うのは白黒じゃなくて、グラデーションだから、マーガリンをたくさん食べて〇〇病になる人もいれば、ほとんど食べていないのに〇〇病になる人もいるわけです。
科学的な情報はあなたの運命を予想することは決してできない。 もっといえばタバコは科学的に身体が悪いことがかなりはっきりとしたデータとして示されている数少ないものだけど、ヘビースモーカーでも長生きする人は長生きする。でもその横で、タバコもお酒も一切やらなくていわゆる「健康的な生活」を送っている人が、がんになったりする。
現実は白か黒かでわかることは ホントに少なくて、常に曖昧な部分の方が多いわけだから、流れてくる情報をもっとゆるやかにみるために、情報に対する抵抗力を持った方がいいんじゃない かな。
-そこは、卵が先か鶏が先かじゃないけど、もうすでに陥っている人たちは抜けられないから悩んでいるんであって…
実はもう一つ考えてきたんですよわたし。
-わあ、なんですか
自分の身体や個よりも先に関係性がある
自分の身体とか自分の個よりも先に関係性があるって考える。
-ほお…
つまり、自分の身体がうんぬんかんぬんっていう話では、常に自分の個が先にある。だけどそもそもわたしたちは関係性の中でしか生きていけないので、関係性が先にある。
たとえばそれは自分の大事な人との関係、親でもいいし友人でもいいし、先生でもいいけれども、その関係性の中で心地よくなるには自分はどう繋がったらいいのかなっていう考え方です。
もしこの関係性の中で自分が心地よく生きたいとするならば、食べ物のカロリーを計ってやせようとすることが大事なのか、それともこの目の前の人と言葉を交わすことが大事なのかって話です。
-つまり現実問題ちまたの情報では、やせたらモテるしそうするといい人とお付き合いできたり結婚できる、そうすると幸せになれるみたいなイメージがあるけれど、実際に目の前の異性を見たときに本当に自分がやせてることでそういう関係になれるかどうかという視点や、本当にそういう関係が幸せなのかという視点を持つ、現実の視点を持つみたいな…
そう、リアルな関係性ってところを先に置くんですよ。
実は「個」にものすごく着目させる思想ってすごく近代的なんです。近代になる前の社会って見てくと「個」はものすごくゆるくて、関係性に応じていかようにも変わる「個」なんです。
今の社会って「自分らしさ」とかってものすごく強調するんですけど、「ありのままの自分」なんてあり得ない。
やっぱり人はどんなときにも役割を背負っているわけですよ。役割を背負っているのは別に 特殊なことではないので無理に「ありのまま」を見つけようとしなくていい、自分らしくしなくていいわけですよ。自分って言うありのままの存在があって初めて関係性を結べる、っていう考え方をひっくり返す。
関係性があって、その関係性によっていかようにも変化する自分のほうがありのまま。そう捉えるとラクじゃないですか? で、そういうふうに関係性を先に置いていくと、不飽和脂肪酸だとか血糖値だとかそんなに重要なんですか?って話なんです。
明日の自分の身体をどうしたいのかではなくて、今ここにある、たとえばわたしといづさんとの関係をどうしたいのかって考えたときに、このカフェラテが300キロカロリーあるとか、そんなことは関係ないわけですよ。
いわゆる心理学的生物学的なアプローチだと、どうしてもまず「個」を見ましょうとなるわけなんだけど、そもそも先にあるのはあなたではなくて関係性なんです。そういうふうに捉えると、周りから入る身体へのメッセージってそんなに重要なのかな?ってなりませんか?
-すごいすごい、ほんとや…
結構がんばって考えてきたんだけどどうかな、ダメかな?(笑)
-いや、すごいと思いました。それは逆に言うと、目の前の人と生身でコミュニケーションするってことが、何らかの理由でできんくなったところから、数値の世界への移行が始まってるとも言えるなって思いました。
で、治していこうっていうアプローチは今のところ、認知行動療法にしても対人関係療法にしても「あなたを変えましょう」というスタンスなんですよ。
でもそもそも、あるのは先に関係性であってあなたは先ではないわけなんですよ。で、もし関係性を取るのは嫌だ、食べ物と対峙して生きるって生き方があるとするなら、わたしはそれでもいいと思う。あなたが決めた生き方なんだから。
でも、もしそれが嫌なんであれば、身体よりも先に関係性がある、という捉え方をしてみる…。あえてがんばって考えるとすればこんな感じかな(笑)。
-ありがとうございます!
他人の指標から自分の心地よさへ
わたし思うんですけど、摂食障害の大変な人がカロリー計算したり、体重測ったりするのはやめたほうがいいんじゃないかな。3カ月ぐらいやめてみたらいいのにって思う。
-気が狂いそうになるかも…
気が狂っちゃう? そうか…。
なんかわたし意識的にそういうことをしていて思ったことがあるんだけど、体重を気にせずに食べてる時って、肉を食べてなかったら肉が食べたくなったり野菜を食べてなかったら野菜を食べたくなったりして、これが身体知なんだろうなって思って。
-身体知ってそういうことも含まれるんですね。
そういう意味でもわたしは使っていて、たとえばお腹がいっぱいになったらもういいかなとか、そういう、そんなに自覚しないでもいいコントロールが身体には備わっていて、たぶんちゃんとその人それぞれのちょうどいいあたりってあると思う。
そのちょうどいいあたりで自分の身体がやってきたのを、常に自分の身体を外から見て意識的に苦しい調整をしようというのは相当苦しいと思う。
自分がもともと持っていた身体知を取り戻そうとする ときに、混乱は起きるかもしれないけど、やめちゃうっていうのはありだと思う。でも狂っちゃう?
-計るのをガマンするってのはやっぱり気が狂いそうになるかな…。程度にもよると思うけど…
だからほんとに体重という数字に準拠してるんでしょうね。体重が人生の目的になっちゃっているとそうなのかもしれない。
イチローがバッターボックスに入ったら、まったく同じことをしないと気がすまないみたいに、体重を気にして生きることがルーチン化しちゃってるわけでしょ。そういう完全にルーチン化しちゃったものを元に戻すには、最初の始動ってのは大変ですよね。
-ルーチン化しちゃったほうのそちらが身体知になってしまっている。
わかるわかる。
-入れ替える必要がある。
慣性だな…。一番初めの始動は一番物理学的に力が必要だけれど、動き始めてしまったらもう力はいらない。
だからたぶんほんとに苦しい、狂っちゃいそうっていうのは一番初めのところなんでしょうね。だからそこさえ回っちゃえばあとは慣性。ボーリングの球みたいにまずは転がしてしまう…。
数字に準拠させるのを意識的にやめるのが難しかったら、とりあえず情報を少し斜めから見てみる。ちょっと小ばかにしてみる。
-そっちはまだできやすいかも。
じゃあ、とりあえず小ばかにする。小ばかにする中でほんとにこれ必要かなってことを考える。
ダイエットがいけないとは思わないし、綺麗になりたいのがいけないとも全然思わないけれど、ただそこに準拠点が移り過ぎていると苦しいだろうし、常に他人の評価の中で生きることになる。
-ご著書にも何度も書いていらっしゃったけど、他人の指標の中で生きることにハマってしまっている状態なんですよね。
自分の心地よさの中で生きるっていう感覚を完全に忘れちゃってる。
「個」よりも先に関係性を置いた場合、たとえばあの人と話したら心地よかったなとか、失われてしまった心地いい準拠点が戻ってくるわけです。
あなたが生きる場がどこにあるかって考えたときに、今あるこの関係性の中を生きようと思えば、外からなんて見えないわけです。で、その瞬間にもし少しでも心地よい瞬間があったならば、それは本当に今この瞬間に自分の身体とともにあるということなんです。
その瞬間を増やすためには、わたしはいわゆる自助グループみたいなものは有効だと思います。心地よいポイントを、今現実にあるネットワークの中に見出せるかですよね。
しかもそれをするときに自分の身体よりも関係性が先にあると思ったほうがラクだと思う。
-ふむふむ
文化人類学を知って、私がやりたいのはこれだ!と思った
-最後の、一番聞きたいポイントに移りたいんですけど、磯野さんが今に行き着くまでのことを今のご研究のことも含めて話していただけると。
この本に書いたこととも繋がってくるんですけど、わたしもともと運動生理学やっててトレーナーになりたかったんです。
-体育会系ですよね!
良く言われます。全然うれしくないんですけど(笑)で、面白いことに、自然科学的なアプローチっていうのは人間を捉えているような気がしないんです。
本にも書いたように運動生理学って人間がどんどん細分化されていくんです。最初パフォーマンスの話だったのが筋肉の話になって、いつしか筋繊維の話になってアミノ酸の話になって、みたいにどんどん人間が細かくなっていく。
でも実際のスポーツのパフォーマンスって、筋繊維がどうだとか栄養素がどうだとかではなくて、やっぱりもっといろんな要素で決まってて、もしかしたら朝見た目覚ましテレビの占いの結果が悪かったとか、それが影響しちゃっているかもしれないわけですよ。
そういう風に捉えたときに、人間を細かく切っていくアプローチっていうのは、なんかわたしが知りたい人間のスポーツじゃないって違和感を感じたままアメリカに行っちゃったんですよ。
-その運動生理学のことで?
スポーツのパーソナルトレーナーになろうと思って。でもやっぱりなんかのめりこめない。そんな時に出会ったのが文化人類学です。
いわゆる運動生理学的な、まあ自然科学的な研究って言うのは実験参加者っていうのは人形なんですよ。自分が言った通りに動いて欲しい。たとえばアン ケートに1,2,3,4,5っていう選択肢があったら、そこで選んでもらわなきゃ困る。変なところに丸を付けられたり、それを言葉で書かれたりしちゃ困る。
でも文化人類学ってまったく逆で、対象者から教えてもらうっていうスタンスを取るんですね。むしろ対象者が自由に生活したり話したりするのに研究者が合わせていく。すごいアプローチだなこれって感動しちゃって…。
その授業を受けた3日後にその先生のオフィスに行って、これこれこういうことをやりたいんですけどって言ったら「それはまさに人類学だ」みたいな話になって変えちゃったの、専攻を。アメリカってすぐに専攻を変えられる。
で、突然わたしは人類学専攻になったの。
-あはは
その時に修士の研究で何をしたいか書かなくちゃいけないわけです。でも考えてない当然。突然変えたんだもん。えーっみたいな感じになって、でも身体のことやってたから、身体に関わるアプローチで、しかも運動生理学的なアプローチでは絶対できないことをやりたいなと思って。って思ったときに摂食障害かなって。
-へえええ
周りにもいたし、自分もダイエットしてたし。あとアメリカに行ったときに、今まで自分はぽっちゃりしてるとか言われてたのに、突然わたしはスリムな人間になったんですよ。
-うんうん
それで、なんなの?これってなんかくだらないぞって思って。っていうのもあって、摂食障害はちょうど今出始めている問題だし、身体っていう運動生理学と文化人類学の接点として捉えられるからこれにしようと思ったのがきっかけなんです。
昔から「こういうものです」的なことが苦手だった
-そもそも、わたしがやりたいのはそれじゃないって、分割していくことに違和感を持つっていうのは、どうしてそうなのか思い当たることはありますか?
わたし、なんか昔から簡単に納得できないってところがあって、小学校?中学校のときかな?マイナスとマイナスをかけたらプラスになるっていうのがあったでしょう。意味がわからない。なんでマイナスとマイナスをかけたらプラスになるの?みんな「そういうものだから」ってやってるけど、「そういうもの」じゃ理解できない。引き算と足し算はわかる。
-そうですね、そういわれてみればなんか、不思議ですよね。どうしてマイナスかけるマイナスがプラスなんだろう。
先生に聞いてもイマイチ腑に落ちる説明が返ってこないんで。なんかそういうふうに、「こういうものです」みたいなことが苦手だった。
子どもとはこういうものだとか、女とはこういうものだとか、ある種のそういうものだ的な決めつけっていうのが苦手だったの。
それで、たぶん人類学みたいなそもそも「こういうものだ」っていうのはどういうふうにできてるの?って調べていく学問があったんだって。当たり前がなぜ当たり前として成立しているのかを考えていくわけです。この本でも「なんでわたしたちは食べるのか」って、ある種当たり前ですよね。そこの部分を見ているわけです。
-こういうものだっていう前提が腑に落ちない…。なるほど、とても共感します。それはそうと、摂食障害という題材を選んだっていうのは偶然だったんですね。
でもずっとやってきたのは、いわゆる摂食障害が生物学的 心理学的 社会学的に絡まりあって起こるっていう、あのモデルがどうも腑に落ちなかったから。で、15年もかかっちゃったと。
-15年ですか!このインタビューを始めたのと摂食障害に取り組み始めたのとは同じ時期ですか?
いや、このインタビュー自体は2006年から始めてるんですけど、シンガポールの時期があったから。実際、摂食障害に取り組みはじめたのは2000 年から。2001年にシンガポールに行って修士論文書いたのは2003年。それからずっとやってて、2015年にこの本が出たんですよ。
-じゃあ修論はまた別の?
シンガポールの摂食障害。この本の家族モデルのところはわたしがシンガポールにいたからこそ書けたところ。
-日本とシンガポールの摂食障害のとらえ方は全然違ってたって書いてありますね。
わたしがみなさんに言いたいのは、みなさんが正しいと思っていることって意外と正しくないんですよと
-つくられた正しさですね。声を大にして、ぜひ言い続けてください。
エラそうに言ってる人ほど疑いましょう。
-いいぞいいぞ(笑)。偶然とは言えよくぞ摂食障害を取り入れてくださったというのが一当事者としての素直な感想です。
最初は自分自身が、治療モデルの枠組みにはまっていた
-15年間やってみてどうでしたか?
実は自分自身が治療モデルの枠組みから出るまでにすごく時間がかかった。
-それはどういうことですか?
結局さっき出たいわゆる「原因は?」っていうあの思考からまったく抜けられなかった。
-へええ!
だからシンガポールに行ったときも「社会的要因」という部分に時間を費やしちゃって…。そこから自分自身がそこにハマってるって気付くまでにたぶ ん10年以上かかった。
そのぐらいわたしの中にも刷り込まれているモデルだったの。これは病気である、治すべきものであるって。
-じゃあ最初の10年間は治すべきものという前提で…
そこまで考えてなかっただろうけれど、それは頭にはあっただろうね。要因を考えてたってことは多分そう。
で、ある時インタビューをしていて「なんでこの人は美味しいって言わないんだろう」ってふと思って。こんなに食べ吐きして、食べることに興味があるのに、食べてるときの話で美味しいってでないよな、それはどうしてだろうって。
-素朴な疑問が浮かんだんですね。
すごく食べ物に興味があってあんなに食べ物のことばかり考えてるのに、いざ食べるときになったら全然美味しそうじゃないんだもん。ヘンでしょ?
-で、なんでキャベツじゃ過食できないのかとか、そういう「食べ方」みたいなところにどんどん…
最初は相手にされませんでしたけどね。まあ今でもそうかもしれないけれど(笑)。インタビューしていたその語りが、わたしに向こうから提示してくれた何かですよね。抜け出るきっかけを教えてくれたのは。
-それこそ当事者から学ぶっていう…
まさにそう。
-その疑問から始まって、そうか!食の準拠点がローカルじゃないんだ!って…
そこに行ったのは、美味しいって感じられたりとか心地よさを感じる時には、自分自身の身体とある種いい感じで向き合っている時なんですよね。
だけどそれを全然できなくなっちゃってるんだなって話を聞いていったらすごいわかって。今ここにある自分というところに自分を置けないという状態なのかもしれな いと。
-文化人類学を始めて最初に取り組んだ摂食障害というものを、15年かけて文化人類学の真髄というか本質のところに行きついたんですね。
やっぱり最後の最後に残ったアプローチっていうのは文化人類学の定石である文化相対主義です。
いい悪いをつけずにただ単純にそこで起こっていることを丁寧に読み取っていこうというアプローチ。これがやっぱり最後に残った。
次は医療者を当事者としてみてみたい
-今現在のご研究のこともお聞かせください。
今…結構ずっと当事者の話ばかりであまり医療者の話を聞いていなかったので、いわゆる治療する側の話も聞いてみたいなあと
-へええ
漢方とか循環器の分野でフィールドワークをさせてもらっています。
-なんでまた循環器?
たまたま(笑)たまたまそこに入れたから。
-なるほど。医者と患者の関係性みたいなものをフィールドワークしたいと。その時にたまたま循環器だった。内科でも小児科でもよかったわけですね。
文化人類学って当事者を真ん中に置いた学問と言えるとしたら、今やっておいでるご研究は医療者が当事者なんですね。
そうです。
-ふーん、おもしろい!それはちょっと興味深いですねえ…。
やっぱりどうしても患者、当事者目線で見てたから、医療者はある種画一的に見てしまっていた部分があって、だけど医療者もすごく色々だし、 やっぱり悩んだり考えたりもするわけで、医療者を人間として見たときにどういうことが見えてくるのかなってことに関心がある。
だから介護とか医療とか、いろんな医療に関わる人たちにインタビューさせてもらっています。
-何か感じることはありますか? 今の時点で。
医療者側もものすごく答えがわからない中でやっていて、だけど患者さんは答えを求めてるっていうところの難しさっていうのは思いますね。
-それって摂食障害もまさにそうじゃないですか。
やっぱり特に医療にいればいるほど、すごく人の生き方とか命とか不確実なものだから、どっちかと患者さんは不確実性を消すために医療現場に現れるから…。良心的なお医者さんであればあるほどそこは悩むんだと思う。
-おもしろーい。最初はいわゆる患者を当事者として摂食障害やりました。次は医者を当事者として医療を見ています。じゃあその先は?
どうなんだろう。これまでどっちかと言うと応用チックなところをやってたから、いわゆる人類学者が読まなきゃわからないような、そういう研究も必要なのかなあって思ったりもしています。
-文化人類学と一緒に生きていくことは確かっぽいですね。
それは思いますね。ほんとに、この学問に出会えなかったらわたしは多分、路頭に迷ってたんじゃないかと思う。
わたしみたいな変人を救い上げてくれる学問があってよかったみたいな(笑)
-あはは(笑)。そのままぜひずーっと続けてください。医者が当事者のご研究もすごく興味があります。
病気には「人間ってどんな生き物なんだろう」ってことが顕現されてくる
やっぱり病気みたいなものをやってきたのは、そこに人間らしさが出るからだと思います。人間って何にも起きないときには、惰性で生きてるところがあるけれど、病気みたいなものを持ったときに一番その人らしさが出る気がする。人間ってどんな生き物なんだろうってのが多分そこに出てくる。
だから摂食障害の話もやっぱり食に狂いが生じているからこそ、人間にとって食とはなんなのか?っていうのが実は一番そこに顕現されてくる。
-うんうんうん
不思議なものが好きなの。不思議なものに対する関心てのがある。
-不思議なものに対する純粋な関心から始まってるってことですね。このご研究も。ありがとうございました。あとメッセージがあればお願いします。読者のみなさんは、たぶん、楽になりたいって願っている方が多いはずです。
健康に関する情報は斜めに構えて読みましょう。
-ほう、あはは、格言ですね。
わたし運動生理学やってたから、90年代の後半って脂肪を燃やすために20分ぐらい運動しろって言われてたんですよ。
-ああ、ありましたね。
ところが10年も経たない間に、いや2,3分で燃えるってなっちゃった。なんなのこの変わり方は?って。あんなにまことしやかに本とか出てグラフとかまで載ってたのが、10年ぐらいでバッて変わっちゃってるわけです。そのぐらい、情報と言うのはあやふやです。
こんなメッセージでどう?
-いい、いい。ありがとうございます。
磯野真穂さんプロフィール
磯野 真穂(いその まほ)
国際医療福祉大学大学院講師(博士【文学】)。文化人類学者。1999年、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業
2003年、オレゴン州立大学応用人類 学修士課程修了(応用人類学)
2010年、早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。早稲田大学文化構想学部助教を経て現職。
2000年より摂食障害の研究をはじめ、シンガポールと日本でフィールドワークを行う。
現在は主に現役の医療者に向け文化人類学を教える傍ら、医療現場でのフィールドワークを続けている。
著書に『なぜふつうに食べられないのか―拒食と過食の文化人類学』(2015、春秋社)