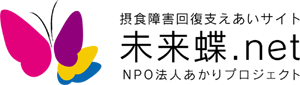HOME > いろんな人の声 > ドクターに聞いてみよう! > vol.3 香山雪彦さん

摂食障害に苦しむ人たちや、その家族のグループ「福島お達者くらぶ」のスタッフを十数年間に渡って続けておられ、多くの摂食障害のご本人と接して来られた香山雪彦さん。
神経生理学の教授でもいらっしゃる香山さんが、何故、どうして、どんなふうに摂食障害と向き合って来られたのか、その軌跡や摂食障害に対するお考えなどをお聞きしました。
(2010/1/9 取材・文 あかりプロジェクトいづ)
初めて摂食障害に触れたとき、それまでの価値観を根底から覆されました
―まず、摂食障害に向き合ってこられた軌跡と現在の取り組みを教えてください。
私が教えていた学年にいた学生で過食症で留年を繰り返していた人への支援を頼まれたのが始まりです。
よく知っていた学生が「自分の友達をちょっとサポートしてやってもらえませんか。」と連れてきたのです。摂食障害のことなど何も知らないままに引き受けてその人に関わって、それまで自分の知ってた世界がどれだけ狭かったのか、人の心というものがなんと奥深いものか、というよりは、なんと恐ろしいものかということに衝撃を受けました。人間40年くらいも生きていると、それなりに自信を持ってたのだけど、その自信を打ち砕かれました。
それで摂食障害の勉強をしてみようと思って手当たりしだいに本などを読んだのだけど、どの本を読んでも関わった彼女と違うんじゃないかと思った。専門家の書いた本だってそうです。
その中で唯一、本人たちが書いた手紙を載せたNABAの「いい加減に生きよう新聞」から了承を得られたものをまとめた本『カナ リアの歌』を読んだ時に、あ!これが本当なんだ、と思って、すごくよく理解できたんですね。
ちょうどそのころ、福島で今の「福島お達者くらぶ」、そのころはまだ「福島摂食障害者の会」という名前で、それじゃあんまりだというので若い人たちが 「お達者」と名付けた会が立ちあげられました。
毎月1回のミーティングですが、最初の数年は毎回、僕が『カナリアの歌』で感動したNABAのスタッフの方たちが来て司会をされてたんです。それで、「僕も加えてください!」と言ってお達者くらぶのスタッフに加わったんです。
そこで本人の人たちの話すことを聞きたい気持ちもあったけれど、臨床の現場も知らない人間ですから家族ミーティングの方に入りました。そこで話を聞いているうちに、「将を射んとすれば馬を射よ」と言うように、摂食障害に対応していくには家族が大事かなと強く思うようになって、それ以来ずっと家族会に関わってます。
―摂食障害の当事者の集まりには参加してないのですか?
本人の人たちの集まりは自助グループに近い形なんです。受付などのためにスタッフが一人入ってますが、その人は始まったら口を出しません。これまで17年やってきましたが、最初は色々とすったもんだがあったけれど、この10年以上、できるだけすべて本人たちに任せよう、ということにしています。よほどのことがない限り、スタッフは口を出さない。できるだけみんなが違和感を持たずに話せるようにスタッフは固定しよう、ということで、一番優しい看護師が入ってます。司会は数回以上参加している人の中からジャンケンで決めるとか。そうやって、自助に近い形でやってます。
しかし、家族会の方は自分たちだけでやっていくのはなかなか難しいです。それは、親の世代は長年生きて生き方が固まってますから変わりにくく、外からちょっと違う考え方を示してあげる必要があることも多いし、自分たちだけでやると中心になる人がその仕事自体に依存を起こしたり、あるいは燃え尽きちゃう。ただ、ちょっと僕たちが口を出しすぎたところがあったりして、今また、やり方を変えようと試行錯誤しています。変えるのはなかなか難しいところもある のですが。
―先ほど、人の心がなんと恐ろしいものかと衝撃を受けたとおっしゃいましたが、何を恐ろしくお感じになったのでしょうか。
その人たちは生きていけないくらいのものを心に抱えてしまっている、それがいろいろな形で吐き出されてくるわけで、それも怖かったし。それに、関 わっていた人の態度がいきなりコロッと変わったことがあって、2、3日前まで必死にすがってきていたのに、急に「もう私に関わらないでください。」と言われて。今なら、ものすごくよくわかる。けれども、当時はそういうことが全然理解できなかった。一体どうなってるんだ?と。裏切られたのとも ちょっと違うけれども、理解できなかった。そういうこと全部含めて、恐ろしいと感じました。
―恐ろしいと思ったりショックなことがあったら、そこから目をそむけたくなったり、もうこりごりだと思ってもおかしくないと思うのですが、そこで香山先生が食らいつかれたのはなぜですか?
自分が知らなかった世界だからショックを受けて。それはもう本当に、それまでの価値観みたいなものを根底から覆されたわけで。やっぱり勉強し直さなきゃしょうがない、という感じですね。
―先生はもともとお医者様でいらっしゃったんですか?臨床医でいらっしゃったんですよね。
医師の資格は持ってます。実際8年間臨床の部門にいて、といっても麻酔科・ICUですが。しかし実際に臨床医をやったのはどれくらいだろう。5年はやってないかな。あとは留学したりして研究だけしてましたから。
―医学部に入られたのは、もともと医師になろうという夢がおありだったんでしょうか。
あんまりなかったですね。僕は、父親が大学の生物の教師で、父の友達がニホンザルの研究をやってたんです。イモ洗いをするサルとか、知ってますか?そういうのがものすごく面白くって。だから、大学に行ってサルをやろうと思ってたんですよ。
ところが、高校3年生の1月くらいになって、「サルよりも人間の方が面白いかな」と、ふっと思ったんです。それで急に医学部に変えたんです。だから最初から、医者になりたかったいうよりは、どちらかというと研究者になりたかったんですね。それで、いろいろあって、脳のこと、それも脳生理学をやってみたい、と思うようになりました。人間の情報処理がどうなっているんだろう、と。
―人間の脳の中の情報処理ですね。
そうです。コミュニケーションが必然的に関わってくるけれども、脳の中でその情報がどう処理されているかということが基本にある。それをやろうとしてたわけです。
研究を目指しても、最初は全く違う分野も考えていたのだけれど、いろいろな事情や縁があって、神経生理学を専門にするようになったというのが、現在の職業です。
パワーゲームではなく、一緒に並んで、この世の中を歩いていきたい
―支援を頼まれるというきっかけがあったにせよ、研究者でいらっしゃる先生が、どうしてここまで深く摂食障害に関わっておられるだろうという点に興味が湧きます。
臨床医をしていたときには自分の人生これでいいのかと疑問を感じていたけれど、研究者になっても、やっぱり何か合わないものを感じてたんですよ。
研究者というのは実はパワーゲームの世界ですから。大学の教師もパワーゲーム。自分が思う方向に大学を動かしたいというような思いがあるんですよ。特に僕は同じ年の僕と全く違う考え方をする同僚の教授とよく対立したんです。向こうは政治的に動きたい。僕は、摂食障害の人たちに関わりだしてたから、そういう政治的なことに関わってパワーゲームに身をやつすと、絶対に摂食障害の人たちに信じてもらえないだろうなと思ったから…。
実際、摂食障害ってパワーゲームの病気なんじゃないかと、僕は思うところもあります。例えば、お母さんとパワーゲームやってる。お母さんになかなか勝てないから摂食障害になって必死に訴えながら生き延びている、そのお母さんをコントロールする唯一の手段が過食だったり、拒食だったり、という面もあるんじゃないかと思いますね。
お母さんに、愛してると言ってほしい、という人がいっぱいいますね。ある人たちは「そんなの、諦めようよ」と言うんだけど、諦めない。母・娘の関係というのはそんな簡単なものじゃないですからね。それを、僕はパワーゲームだと思ってる。
だから、僕自身がパワーゲームに身をやつしながらいくら手を差し出したって、それは信じてもらえないと思う。だから、大学の中のパワーゲームは止めることにしたんです。その争いから身を引きました。僕は大学の外に活動の拠点を移す、という感じですね。だけど、講座主任・教授としてやっていく時にはやはりどうしてもパワーゲームが必要なこともあって、講座が活動するためのお金を集めてきたりしなきゃならない。それが、もうあとちょっと残ってるんですよ。さいわい、今年は科学研究費などのお金がたくさんもらえたので、これでそういった仕事は終わったと思ってます。
―パワーゲームの世界から身をひかれたのですね。関わっておられる摂食障害の方との信頼関係のほうを重視なさったわけですね。
僕は、なぜか人を捨てられないんです。向こうから離れていくのは自由に離れてくれていいんだけども、僕からは捨てられない。どんな人も。けど、人と真剣に向き合い続けるということは大変だったですね。本当に大変だった。
―人を捨てられないという先生の本質みたいなものがあるからこそ、ここまでこの苛酷な摂食障害と向き合うことができたということでしょうか?
それがなぜ摂食障害だったのかというのは、今だにあんまりよく分からないけど、自分に一番合っていると感じますね。
僕は、自分の本質は治療者や援助者では絶対にないと思っている。そうしたら本質は何かと言うと、同行者です。今は助けてあげたい、手を差し伸べるという立場であるとしても、いずれ一緒に生きていく人間だと常に思っている。一緒に生きていきたい。心を通わせながら一緒にこの世の中に並んで生きていきたい、という思いがすごく強いんです。 僕が深く関わるのは「この人とは一緒に並んで歩いていきたい」と思う人たちなんですね。
その人たちは、自分だけよければとは絶対に思わない人たちですね。必死になって自分をさらけ出し、必死になってすがってる人たちであっても、そんな気持ちはないですよね。その人たちが、いずれは一緒に並んで生きていく立場になるんだということ、お互いに依存しあったり試したり試されたりするのではなく、 いずれは自立し、人と心を通わせながら生きていくようになるということ、それを理解してくれるかどうか、それが僕には一番大きいかなと思うんですよ。
それは相当時間がかかったりもするのだけれど、今は必死になってただ生き延びようとしていても、いずれは一緒に並んで生きていってもらえる人になるだろう人た ち、そういう人たちが、僕が関わる中で一番長く残っていきますね。
―香山先生の中での理想の人と人の関係が、摂食障害の私たちの成長の過程にどこかぴったりあてはまるものがあると…
こういう人がたまたま出てきた、というだけで、そういうのを求めるところは全然ないんだけど…。
もう一つ、僕は人と話していて、「あー、ここはわかってもらえないみたいだな。」とよく思うことがあって、それは何かというと、嫉妬心なんです。僕はなぜか嫉妬心がほとんどない人間なんです。これは、不思議だと言われるんですけど、そうだからしょうがない。たとえばもし家内が誰か別の男の人と仲良くなってそっちに行きたいと言ったら、「う~ん、まあ、しょうがないなあ」と言うだろう人間なんですよ、僕は。自分が思いをかけた人が誰か別の人と仲良くなって、そっちに行くようなときに、もし相手さえよければ一緒にそこへ交じりたいくらいの思いがあって、そんなふうに僕には独占欲がないんです。
そこのところは、摂食障害の人たちと関わってて、自分がそうだからついそのつもりで関わってしまうと、向こうがそうでない思いを僕にかけてしまうことが あって、それが共依存を辞さないくらいに関わったときに苦しいところなんです。それはすごく苦しいですね。僕とすれば、自分のそういった思いがあるのだけれど、ところが相手はそういうわけではないというのが、自分が共依存を起こして苦しんできた原因だろうなと思います。僕がもっと嫉妬心なんかがあって警戒心があったりしたら、そういうところは危なくて手を出さなかったのかもしれないですからね。けど、そんな嫉妬心、独占欲のない人間はどうも少数みたいです ね。その辺がちょっと僕の特殊なところかなと思いますね。
―そこのところも、摂食障害というのが関係あるようなないような…。パワーゲームの病気だとおっしゃいましたが、嫉妬がないということはパワーゲームがないということにもつながる気がしますね。
パワーゲームからは割と簡単に降りられるということですね。僕は大学のなかでどういう立場になりたいというというものが全然ないし、ふつうに生活できれば特にお金もいらないし、だから公然と意見を言える。だから今、大学の中で中枢部の人たちには一番うるさい、目の上のたんこぶになっていると思いま す。だけど、そこに嫉妬心やパワーゲームの要素をまったく含んでないかというと、そうではないだろう、少しはあるだろうとは思いますが、相手を落とすために単に上げ足を取るようなことは絶対にしない。
しかし、実はコントロール欲求はものすごく強かった人間です。自分が相手をどうしたい、こうなってほしい、というのはありました。摂食障害の人の目の前の何か大きな障壁があったら、それを前もって取り除いてあげたくなる人間です。けど、それをしたらすごく怒らせてしまったこと、そのために逆にその人の成長を遅らせてしまったことが何度もあって、一切そういうことをしなくなりました。それはすごく勉強させてもらいました。
共依存には、何度も陥りました
―共依存ということについて、著書に「溺れている人にこちらから手を差し伸べても、 向こうからその手につかまってくれなくてはどうにもできない。こちらからつかみ挙げようとしたら、こちらも引き込まれて溺れてしまう」という記述があった と思うのですが、どのようにしてそのお考えに行きついたのでしょうか。
それは、実際に共依存に落ちたからですよ。何度も落ちました。ひょっとして誤解されたら僕は大学を追われることもありうるかな、というようなことも。それくらいのことがいっぱいあります。それを厭わなかったから、関わるみんなが最初から本当の姿を見せてくれたのかとも思いますけど。
―その兼ね合いが…
難しいですよね。今なら、共依存に陥らなくてもすんなり手を差し伸べてあげられるかなと、やっと、ちょっと思います。それは、やっぱり泥沼の中で 教えてもらってきたことですね。そうでなかったら教えてくれなかったのだろうと思います。それは、苦しかったですよ。むちゃくちゃ苦しかった。相手は若い 女性ですからね、これは難しい。むちゃくちゃ難しい。
けれど、本当にハイヤーパワーのおぼしめしに導かれてきたと思いますね。僕は、ハイヤーパワーというのは、神様のような人間を超越したものではないと思っていて、それは人間が、ホモ・サピエンスという現存の種が確立して何万年か、その間に営々と蓄えてきた知恵、その間の何代も経てきた中で淘汰されてきた特性、一人の人間の中でも意識に上ることのないまま脳に刻印されている膨大な記憶、そういったものが全部積み重なったものがハイヤーパワーの正体であって、それは人間そのものである、と思ってます。そのハイヤーパワーにたくさん助けられてきて、すべての人に対する感謝、過去の人にも今の人にも感謝を強く感じています。それが僕には大きいと思いますね。
―私の持論なのですが…、自分から救いの手をつかめない状態の方っていらっしゃいますね、でもその人の手を誰かがつかんだらその人が自分の持つ力を発揮して歩いていける可能性があるのだったら、やっぱりこっちからつかみに行かなければならないんじゃないか。こっちからつかみに行って、つかみに行った私が崩れなければ、しんどくなったり倒れたりしなければ、私さえ立っていられるならば、どんどんつかみに行った方がいいんじゃないかと思ったりするんです。そのために、自分を強く磨いていこうと。
共依存という言葉、概念はとても必要な概念だし、この言葉があって助かったことが私にも何度もあるんですが、ただ、この言葉が一方で、本当に必要とされているもの、システィマティックなことでは解決できない人間性の部分の何かに対して、援助者のシャッターを閉じさせてしまっている面もあるのではないかと感じたりしています。
たとえばカウンセラーをしているような心理士の人たちでも、そこで引き込まれる人たちはいっぱいいるんですよ。心理士のトレーニングを受けた人た ちは、そういう時はどうすると教えられているかと言うと、自分自身がスーパーバイズしてもらう先生を持たなければいけない。それは、自分は片方の手でどこかにつかまっていて、もう片方の手を差し出してあげるということになりますよね。そういうシステムが必要な訳ですよ。
ところが僕なんかはそういうのが全然なくて、ただ一人で勉強して活動していると、そういうつかまるところがないですよね。だからよっぽど自分がしっかりしてない限りは落ちるわけで、まさに落ちてきたわけです、僕は。そういう中で、幸いなんとか決定的なダメージになる前に勉強したという形でまた這い上がれたと思います。
そんなふうにまさに共依存を通して勉強してきて思うことですが、溺れているのが例えば小学生ならば、こちらから水の中に手を突っ込んで引き上げてあげなければしょうがないと思いますよ。だけど溺れているのが思春期を過ぎた人たちならどうするか。これは難しいです。
自我というものがすごく芽生えてきていて、そこに手が差し出されていると、その手が本当に自分を救ってくれるかどうかということを必死になって試してくる。それに引き込まれてこちらが水に落ちることもよくあります。そうなると2人とも破滅ですからそれは避けなければならないけれど、どうしたらよいか、答えはないんですよ。本当に答えはな い。
私たちの大学に優秀な成績で現役で入ってきた女性で、医学部に来たのが医者になりたくて来たんじゃなくて、お母さん・おばあさんの夢を背負わされて、 「○○ちゃんは当然医学部に行くわよね。」と言われて入ってきた人がいました。だけども入ってきてみたら、いろいろと問題が出てきて2年生で留年、さらにもう1回留年して3回目の2年生をやることになって、その留年が決まったときに、僕は手紙を出したんです。よかったら連絡ください、と。そこで2回くらい長いメールのやりとりをして、相当いろんなことが書いてありました。お母さんやおばあさんの見果てぬ夢だということも、そのメールでわかったことです。
ところが、当然その人には大学の学生相談室も関わっていたのだけれど、学生相談室を担当している臨床心理士の人たちは僕とは全く違う考え方をしている人たちでした。たとえばその人たちは、福島お達者くらぶを絶対に認めない。過去に、その人たちが精神科病棟で診ていたある摂食障害の人が、認知行動療法をやっていてかなりコントロールが良くなってきていたのだけども、入院中にお達者くらぶのミーティングに出たら、そこでみんなに「食べ吐きしていいのよ。」と言われて、食べ吐きに戻った。
そんなことがあって以来、入院患者さんたちは福島お達者くらぶ出入り禁止なんです。僕から見ると、そんなことで簡単に戻るなら、退院したらすぐ戻ってしまうか、別の行動とかアルコールとかに行ってしまうに違いないと思うのですが。そのあたりの考え方が全く違う。彼らは自分たちが治してあげられると思ってるんですよ。
その辺の考え方が全く違うので、もし僕がそれ以上に手を出すと学生相談室と全く違ったことを言いますよね。そうしたら彼女は混乱するじゃないですか。そ れは避けなきゃいかんと思って、「本当に困ったことがあったら、あるいは誰かに話がしたい時があったら、いつでも僕の所に連絡くださいね」ということを書いて、そのあと連絡がなかったんです。
どうしてるかな、と気になりながら、学年末近くなって学生部長から「彼女は今年も進級させられないから除籍です」と言われました。「そこまであんたたちは何もしなかったのか!?」に対して、「学生相談室が手を差し出していたけど、それに乗ってこなかったから しょうがない」と。それでいいのか!?と思ったけれども、それが大学の規則だから、僕が手を出せるところじゃないんですよ。3月の教授会決定があって、 その次の日に彼女は自殺しました。
それが今でも僕の心に一番の傷として残っていますね。本当に、どうしてあそこでもうちょっと追いかけてやらなかったかと思います。向こうからつかまってこなかった訳で、僕があれ以上追いかけても、つかまってきたかどうかはわからないけど。今でもつらいですね。本当につらいです。
だから、本当に答えはないんですよ。水の中に手を突っ込んで、ひっつかんで引き上げてやる、そこまでこちらから手を出すのか。だけど向こうからつかまってもらわなきゃしょうがないのか。だけど、ものすごく頭がよくてものすごく感受性が高くって、こっちのちょっとした迷いなんて全部見抜いてしまう人たちですから、あやふやな気持ちがちょっとでも混ざってたら絶対につかまってこないですよね。だから何もかも振り棄てて彼女を救いにかかったら、ひょっとしたらつかまってくれたかもしれないけど。しかし、それ以外も何人もの人がいますから、彼女一人に関わってやることはできないし。どうしたらよかったんだろうな。
本当に無念だし、ものすごく心が痛い。
本人のみなさんには、なぜこんなに苦しんでいるのかという本質を教えてもらってきました
―先生は、神経生理学という分野の脳や神経の専門家でいらして、でも最終的にはこれは人と人のつながりの温かさを信じたいけど信じられないことの障害なんだとおっしゃってますね。
僕は脳生理学を専門にしているけど、研究テーマとして摂食障害を考えたことは全くないんですよ。この人たちを研究の材料には絶対に使わないと、関わり出した時に誓いました。
そうじゃなくて、純粋に人としての関係でつながりたいと思ったので。だから今でもそういう関係で論文を書いたことはないです。
―一番大切な信頼関係とか温かいつながりというものが、そのことで亀裂が入る恐れがあるということですか。
そうです。研究テーマにはしない。ただそこで感じ取るものだけを糧にしていくんですね。いろんなことを教えてもらい、そしてそれは自分の心の中に蓄積していく糧になっている。精神科で診てもらっている人が、外来や入院でいろいろ話してても絶対に言わないことをこのミーティングでは言ってくれたりし ています。家族もそうだし。
―絶対に言ってくれないこととは?
やっぱり診療の場というのは、時間も短いのだけども、一種の駆け引きの場ですから。
―より深い所に入っていくのは難しい。
そうそう。しかも直接病気に関係のない、はるかな背景になっていることとか、そういう思いはミーティングでしか聞けないですから。
そういったことを聞かせてもらうのは、もう本当に、教えてもらうという感じですね。心の糧になっていきますね、僕のような立場にいる人間にとって。
教えてもらっていることはいっぱいあって、だけどもそれは僕たちが研究のために尋ねたり、あるいは診療のために尋ねていることではなくて、自然に心に積み重なっていくものなわけで。だからものすごく勉強させてもらっているけれども、勉強のためにミーティングに出ているのではない。そういう感じですね。
その辺は、臨床の場に出ている人とは全然違います。臨床の場に出ている人はなんとかしてあげなきゃいかんのだもの。だけども、なんともならないんだということがわかるようになるまでに時間がかかる。
そんなふうにして教えてもらってきたことの一つだけれど、患者さんや家族の人たちに境界性パーソナリティ障害ということを明確に言う医師がいますが、僕は今、境界性パーソナリティ障害という人格に障害のある人がいるのではなく、そういう状態に陥らなければいけない時間帯や時期があるんだと思ってます。そういう時間を過ぎていくと、その人たちは本当にやさしいですからね。本当にやさしい。時々狂うんだけれども。狂ってまた怒りをぶつけたりする時もあるけれども、そういう時間帯・時期以外は本当にやさしい人たちです。
だから、そういう人格障害なんて人がいるんじゃない。もともとそんな障害があるんじゃないと思ってる。ただ、そういう状態じゃないと生きていかれない時期とか時間帯があるんだ、と思ってます。
―香山先生がおっしゃることが、当事者の私にも、ああ、この先生分かってくださる、というのがあるのは、やっぱりそれだけ沢山のご本人の方と関わってこられたからかなあと思いました。
臨床の場でないところで関わっていますから人数は少ないけれども、深くかかわった人たちが何人かいる。何人かですよ。
その人たちと、何にも知らな いところから、共依存という言葉も知らないままに関わって、そういう中で教えてもらってきたことがたくさんある。治すという立場ではないわけですから、僕はね。
たとえば精神科の医師ならば、指導者たちから共依存に陥ってはいけないよと最初から教えられるし、医者と患者は契約関係だよということを教えられるし、そうやって前もって教えてられたところから診るわけですが、僕は患者さんとしてその人たちを見たのではないですから、そういうものが何にもなかったんです。いきなり本人に関わった。それで、すったもんだを繰り返して。
―先生が教えられてるとおっしゃった、それを言葉にするとどういうものなんでしょうか。
なんでしょうね?
なぜこんなに苦しんでいるのかという本質を教えってもらってきたのか。
要するに、教科書みたいなもの読んだってこれは本当と思えないことがいっぱいあって、これが本人を見てたら「あ、そうなのか」と。「先生、それは違います。」とか言われたりもするわけで、「おおそうか。それはごめんね。」と言うこともよくあるし。まあ、すべてという感じですね、教えてもらったことは。
―先生の著書は、何が起こっているのかわからない、言葉にならない段階の人に、先を行く仲間たちが言葉のプレゼントをしてくれてる感じがします。
こういう本を書くときというのは、プライバシーの問題で症例を混ぜ合わせて書くことが多いけれども、僕は全部本人が書いてきた文章、それ以外の個人にかかわる部分も、全部原稿を書いた段階で 「こういう載せ方をさせてもらっていいでしょうか」と尋ねる手紙を出して全部了承を得ています。それはみんな喜んで使ってくださいと言ってくれた。それで凄まじい、生の声を出させてもらえたというのがこの本の特徴かなとは思います。
自己評価の低さも、学習で変えていける
―本当の病気は、自分の本当の気持ちを出せないところなんだ、とか、遺伝子で決められてしまう変えられない部分と変えられる部分があって、自己評価の高さ低さは変えられる部分だ、と著書で言い切ってくださっているところなど、そのあたりをお聞かせいただけますか。
変えられる部分といっても、特に自己評価の部分ですけど、3歳くらいまでは環境の影響を大きく受けて変化するのだけれど、4~5歳からは変化が起こりにくくなって、長くみても思春期までにはやっぱり固まってしまうわけですよ。固まったらそれは変えられないのだけども、別のことで実質的には変えることができる。
例えば、同じころに固まるものに言語中枢があって、それも4~5歳から思春期までには固まってしまうんです。言語中枢というのは大部分の人では大脳の左半球にあるんですが、その言語中枢になる部分が3歳くらいまでに壊れると右半球の同じ部分に完全な言語中枢ができます。ところが、小学校に行く頃になって壊れると、一応反対側にできるのだけども、少し不完全なのしかできないんです。思春期を過ぎて壊れると、完全に失語症になります。というように言語中枢ができて初めて言語が使えるようになるわけで、それが壊れると言葉が一切使えなくなる。
そんなわけで、僕が英語を習い始めた12歳には言語中枢が固まっていたけど、ところが僕は今、決して得意ではないけれど英語が喋れる。2年あまりアメリ カに留学してましたし、今でもふつうのコミュニケーションに困らない程度の英語は喋れます。最近もアメリカ時代のボスを招いて2週間一緒にいて、最初の 1~2日は言葉を考えてひねり出すのにちょっと苦しかったけれど、あとは毎日ふつうに英語を喋って暮らしてたんです。
それは言語中枢で喋っているのではな く、学習して得た別の脳機能で喋ってるわけです。その証拠に、僕がボスと英語で喋っていたところで家内に「今、何言ってたの?」と聞かれたことがあって、 そのとき「今こういう話をしてたんだよ」と日本語では伝えられるのに、今聞いたばっかりの英語を繰り返せなかったということがあって、僕は学習したもので 日本語に置き換えて聞いたり喋ったりしてるんだということがわかった。
そのように、出来上がったものは変えられないけれども、それをカバーするものは学習で得られる。自己評価の低さという性格も、それは変えられない。三つ子の魂は百まで変えられないけども、別のもの、学習して得たものでカバーすることによって、実質的には変えていくことができる。僕が英語を喋れるのと同じ程度には変えられる。それは断言できます。
そうしたら、その学習にはどうしたらいいのか。それは、自分はここにいていい人間なんだ、自分にはいていい場所があるんだ、自分にはありのままの自分で受け入れられる人間関係を持っているんだ、という経験を積み重ねる以外にないと僕は思ってます。
それを積み重ねるために必死になって試してるんです、みんな。
傷つくことも多いけれど、しかし、中にはそんな経験が得られて、一つ得られたらそれを種に して、そういう体験を積み重ねていける。自助グループというのはまさにそのためにありますよね。ここは自分が安心していられる場所なんだ、安心して自分の言葉を話せる場所なんだと。
そういう経験の積み重ねでしか学習できない。1回や2回経験したってダメです。それを積み重ねなきゃどうしようもない。時間をかけて。時間をかけて積み重ねていく。何年もかかりますよ。英語を習い始めたってすぐに喋れないのと一緒で、時間がかかる。しょうがないですね。
その経験のひとつとして、お母さんとの関係が大きいんですね。お母さんとの関係が安心できるようになるのが大きいのだけども、しかしお母さんが変わってくれなかったらしょうがないですよね。その時はあきらめるしかしょうがないんですよ。けど、あきらめるためには、とりあえず本当の思いをお母さんにぶつけてみなければならない。親なら言わなくてもわかってよと言葉にせずに過食を続けてもだめです。本当の思いを言葉にしてぶつけて、それでもだめなら、さばさばとあきらめて、そうしたら別の人を探せます。
また、時間がたてば必ず解決されるかというと、それは本人次第のところもありますね。本人がどれだけの理解能力や理解しようとする気持ちがあるか。その ような経験を積み重ねるということを理解しようとしなければ、救われるとは言い難い時もあるわけですよ。それは、なかなか難しいところもありま す。
―理解能力というのは、自分に起こっていることを言語化するとか、そういったところでしょうか?
そうですね。言語化の能力ももちろん必要ですし、ちょっとした勇気も必要です。
過去にさかのぼる。ここは触れたくなかったんだけど、というところに触れる。封印していたところを、なんとか解放してやる。そういう勇気です。それを、わーっと出せる人と、本当に勇気を振り絞らないと出せない人と、それ はその人の性格ですよね。いずれにしても、それを安全に出せる場が必要なのですが。
摂食障害は、逃げているんじゃない。生きるためにもがいているんです
―社会参加についてのお考えもお聞かせいただけますか。
難しいですね。僕がすごく深く関わった人たちというのは医学部の学生だったり、看護学部の学生だった人が多くて、そういう人たちは国家試験を通るとうんと楽になるんですよ。医師でも看護師でも働きたいと思ったらいつでも働ける場所があるので。苦しくなってやめても、またしばらくして働くようになったらちゃ んとその場所がある。それはものすごく恵まれてるんですよ。だから社会参加という面でいうと、その人たちは何とか卒業まで持っていければよかった。
しかし、それ以外のいろんな立場の人たちもよく知ってるわけで、その人たちを見ていると、一旦継続して働けるようになると、なにしろ一生懸命ですし感受性も高いし、だから必ず認めてもらえるんですよ。認めてもらえない働き方しかできないときは、まだ時期が来ていないだけ。その時はもうちょっと時期を待たないとしょうがないかなと思うけど、いずれ必ず認めてもらえると思うんですよ。
社会システムがそこまで整っているか、特に今はこの格差社会でそこまで経済的な背景が得られるかどうかは難しいけども、それでもそうやって正社員になった人を何人も知ってますからね。デニーズで働きだして店長になったとか。最初はもちろん短時間のアルバイトで、意地もあってね、そこで頑張って正社員になり、研修を受けて店長に。
そこまで頑張らなくてもいいのにと思うくらいだけれど。店長になったらなったで苦しいんですよ、人間関係なんかがあって。「ヒラに戻してもらったら?」と言ったのだけど、ちょっとしばらく休ませてもらって また店長に戻ったそうです。だから、働く場所さえ得られればとは思いますよね。
―もし認められない働き方をしているのだったら、時期が来ていないんだっていう言葉は、すっごく救われる人が多いと思います。
摂食障害は、もがいているんですね。逃げているわけじゃない。
あるメディア関係にいた人で、一生懸命に摂食障害や性に関して講演活動をしている人がいるのですが、その人の本に「逃げずに○○しましょう」みたいなことがあったから、僕は「それは違うでしょう。逃げてるのではなく、必死に闘っているの ですよ」と言ったことがある。僕は、逃げているんじゃない、生きるためにもがいている症状なんだということを知ってほしいと、僕の本を送りました。そうしたら、「本当にそのとおりですね」と返ってきました。
―食べ過ぎることも、食べないことも、経験したことのない方からはどうしても逃げているという風に見られがちで、私もとても悔しい思いをすることが度々あります。そして、一番には、本人が自分で自分を「逃げている」と責めることがまた、苦しみを倍増させている面があると思うんですよね。逃げているわけでは決してない、その逆なんだとおっしゃってくださる先生の存在、とても心強いです。
今日は、先生の軌跡やお考えをたくさんお聞きできてうれしかったです。ありがとうございました。
香山 雪彦(かやま ゆきひこ)

1945年 京都市に生まれ、子供時代を和歌山市で過ごす。
1970年 山口大学医学部卒業。麻酔科医師として働く。
1978年 大阪大学に移り、神経生理学の研究に専念する。
1987年 福島県立医科大学医学部に赴任。神経生理学講座の教授として学生教育および「睡眠・覚醒の神経機構」の研究にあたるとともに、1992年より精神科医師、 看護師、心理士の有志の人たちと摂食障害に苦しむ人たちやその家族のグループである「福島お達者くらぶ」のスタッフを務めている。
著書に、『食を拒む・食に溺れる心~不安という時代の空気の中で』(2007年 思想の科学社)がある。
「福島お達者くらぶ」ホームページ内にもエッセイ『拒食・過食の人達が伝えようとしていること、その人達に伝えたいこと』が掲載されています